以前、2013年の初レポートでも解説したように、米国が日本に「集団安全保障」を認めるように強い圧力をかけてきたために、現在、日本国内では「集団安全保障」を認めるか、どうかの議論が起きている。冷戦時代が終わり、日本を独立自尊の国にするためには、そろそろ集団自衛権を考えるべきだろうというような日本人自身から出てきた議論でなく、財政赤字に苦しむ米国が、自国の軍事戦略を日本に少しでも肩代わりさせようという米国という軍事大国の都合から、出てきた議論であることに、私たち日本人は、もっと注意を払うべきだろう。
ところで、今まで内閣法制局は、「日本国憲法のもとでは集団的自衛権は行使できない」という解釈をとってきたはずであるが、現在自民党の中では、この集団自衛権を解釈変更しようという動きが出ている。この動きは、あまりに姑息で、法治主義に反する行為だろう。きっちりと国民的議論を喚起し、憲法改正の是非を国民に問うべき課題のはずである。
*(前内閣法制局長官に聞く~集団的自衛権の行使はなぜ許されないのか~阪田雅裕)http://www.chukai.ne.jp/~tottori9jo/etc/syudan.pdf
本日は、5月3日、憲法記念日である。現在、浅学非才な小生でも、日本国憲法は、本当に戦後、機能してきたのだろうかという疑問を持つようになってしまったところである。先日も、後で紹介する「絶望の裁判所」(瀬木比呂志著)という、日本の司法の現状を告発した元裁判官の本を読んでいたら、以下のように書かれていた。
~米軍基地に関する騒音差し止め請求について~
「憲法秩序が条約に対して優位にあることは憲法学の通説であり、憲法上の基本的人権、人格権の侵害に関わる事柄については、国は前記のような行為を行うべき義務がある。アメリカのやることだから国は一切あずかり知らないというのであれば、何のために憲法があるのか?それでは、植民地と何ら変わりがないのではないだろうか?」
(128ページ)
日本国憲法には、三権分立が高々と規定されているが、本当に日本は、三権分立の国であろうか。
ご存じのように実際には、霞ヶ関の官僚たちが、国会議員の代わりにすべての法律を作り、内閣の代わりに政策を立案しているのが、私たちが住んでいる日本という国である。ちょっと考えてみればわかるようにこの行為は、「日本国憲法」第41条に規定された、国会は「国の唯一の立法機関である」に違反していることにすぐに気が付くはずだ。立法府を行政府から独立させるシステムをつくれば、簡単にできることを官僚が、議員を形だけのものにするために、故意にやっていないのが日本という国なのである。
そういった視点で、「日本国憲法」は、正しく運用されているのだろうか。一度、素直に考えて見る価値はあるのではないか。
ところで、「統治行為論」というものを有名にした砂川事件というものがある。「砂川事件」において最高裁は「統治行為論」で押し切る以外に、合憲という判決をくだすことが、できなかったのである。これでは「日本国憲法」は、少なくとも実態において「憲法」=最高法規としての効力を持っているとは言い難い。「砂川事件」の経緯を見ても分かるように、必要とあれば米国からの圧力がかかり、それにより、日本の裁判の結果が動くというのでは「憲法」の存在価値そのものが問われるのが当然だろう。
参考:「日米地位協定入門」http://www.yamamotomasaki.com/archives/1637
また、升永秀俊弁護士の啓蒙活動で知る人も増えてきているが、「一票の格差問題」が憲法第14条違反ということ名目で、全国各地で裁判が、起こされているのが現実である。この状況を逆説的に考えてみると、第96条自体も守られていない事になる。なぜなら「憲法解釈」により事実上の改憲がすでになされていることになるからだ。そういうことなら、改正条項自体に意味がないことになってしまうだろう。
たしかに憲法前文に「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」とあるが、その前提そのものが、担保されていなければ、どうしようもないではないか。
そして、国の最高法規がこのように粗末に扱われているようでは、残念ながら、国民主権、議会政治が本当に日本という国で機能しているのか、どうか、疑問を持つのが自然であろう。
私たちは、日本国憲法の護憲やの改正を言う前に、戦後半世紀にわたってこの憲法が本当に機能してきたのか、もう一度、虚心坦懐に考えてみる必要があるのではないだろうか。
○第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
砂川事件:米軍立川飛行場の拡張計画に反対して場内に立ち入った運動員が旧安保条約に基づく法律に触れるとして起訴された事件であり、アメリカ軍の駐留と旧安保条約が憲法9条に適合しているかどうかが実質的に争われた裁判。
*統治行為論:直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為とし、 統治行為に対しては、法的判断が可能であっても、司法審査は及ばないとする理論
<参考資料>
*現代ビジネスより
一人の学者裁判官が目撃した司法荒廃、崩壊の黙示録!『絶望の裁判所』著者・瀬木比呂志氏インタビュー
最高裁中枢を知る元エリート裁判官による衝撃の告発
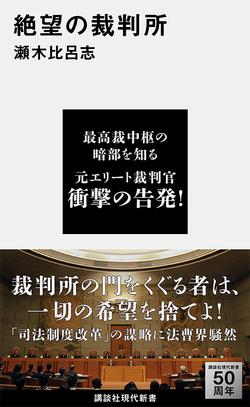
著者の瀬木比呂志氏は、明治大学法科大学院専任教授で元裁判官。民事訴訟法のスペシャリストとして知られ、専門書のみならず、小説や芸術論の著作も多い。最高裁中枢を知るエリートでもあった瀬木氏はなぜ法服を脱ぎ、日本の司法に警鐘を鳴らす問題作を執筆したのか?
背景には、「司法制度改革」導入と相前後して進行しつつある、司法の腐敗と堕落に対する危機感があった。出世や権力ゲームにうつつを抜かす裁判官たちの精神の荒廃と堕落はもはやとどまることがない。一人の学者裁判官が目撃した司法荒廃の黙示録とは?
--過去に裁判所の中枢にいたことのある元裁判官が、このように苛烈な司法批判、裁判所・裁判官批判をされたのは、なぜなのでしょうか? なぜこのような本を書かれたのでしょうか?
瀬木: 本は、一言でいえば、意識よりも無意識、直感や一種の本能、論理や感受性についてもより根源的な部分で、書くものと思っています。僕の本は、専門書も一般書もすべてそうですね。
33年間裁判官を続けて、ことに最後の10年余り、「これではもうこの制度はだめだ、根本的改革しかない」と思うようになっていきました。『絶望の裁判所』の前の本である『民事訴訟の本質と諸相』(日本評論社)の中の制度批判の部分は、そういう思いを抱きつつ自然発生的に補筆を重ねる中で、形を成していったのです。
ですから、その本がきっかけとなって本書の企画が生まれたとき、既に、頭の中では、内容はできあがっていました。あとは、どのように書くかという方法の問題が残っていただけです。苛烈な司法批判になったのも、自分で意図したというよりは、自然にそのようなものとなっていったのです。むしろ、自分としては、もっと穏やかなものにしたいという気持ちもあったのですが、書くときは、自分の中の深い部分の声に従って書くほかないですから。
--このような根源的、包括的、徹底的な司法批判、裁判所・裁判官批判の本を出すことに対する恐れの気持ちはありませんでしたか? 裁判所当局は、本書に対してどのようなリアクションをとると考えられますか?
瀬木: 恐れというより、やはり、自分の属していた組織を批判するわけですから、痛みはありました。一気呵成に書いたのは、長く抱えていることがつらい書物であったということもあります。もっとも、大部の専門書が書けるだけの内容を興味深くコンパクトに凝縮するわけですから、推敲は十二分に行いました。
裁判所当局は、普通に考えれば、黙殺し、頬被りを決め込むでしょうね。もしも反論を行えば、当然僕の再反論も認めなければならず、そうするとさらに都合の悪いことになっていくことは目にみえていますから(笑)。
あと、裁判官を始めとする法律家の中には、ことに匿名で、人格攻撃や中傷を行う者は出てくるかもしれません。そういう人間の存在は、本書第5章の記述からも、容易に想像されることと思います。
--社会的地位が高く、年収2000万円という高収入の仕事を捨てて、学者になられたのはなぜでしょうか?
瀬木: 本にも書いたとおり、三つの評価の高い大学から声をかけてもらったわけですが、二つ目の有力国立大学については、本当をいえば、既にその時点で移りたかった。しかし、収入低下に加え、半単身赴任とそれに伴う年間数百万円の出費があっては無理でした。
明治大学は、私立の中で最も意識していた大学の1つです。大手の中でも、学風が自由で、研究環境や給与水準を含め、総合的な諸条件も比較的いいのです。それでも収入は下がりましたが、別に半単身赴任などが伴うわけではないですから、あまり大きな問題ではないですね。
考えてもみていただきたいのですが、旧ソ連や昔の中国から自由主義社会に亡命してきた知識人が、「こっちのピロシキはまずい」とか、「中華が偽物だ」などといった不平を漏らすでしょうか?(笑) 裁判所における僕の最後の7、8年間の生活は、精神的にみれば、全体主義的共産主義国家にあって亡命の機会を待っている知識人のそれに近いものだったのです。
--最高裁事務総局による徹底的な裁判官支配、統制の実態には驚きを禁じえないのですが、なぜ誰も異を唱えないのでしょうか?
瀬木: 第一に、多数派の裁判官は、感覚が麻痺していて、いかに異常な状況に置かれているかということを直視できなくなっているからでしょう。
第二に、現在の裁判所組織の中にいて異を唱えるのは、それこそ、全体主義国家や全体主義的共産主義国家の中でそれを批判するに等しい部分があるからです。
こうした支配、統制のメカニズムについては、第3章に詳しく記したとおりです。
--憲法で身分保障されている裁判官が、かくも出世に敏感とは驚きました。なぜなのでしょうか?
瀬木: まず、身分保障といいますが、新任裁判官の数は1つの期で昔は60名くらい、今は100名くらい、裁判官全体で現在3000名弱。それで、10年に1度の再任で毎年5名程度拒否される者が出て、事実上の強要に近い肩叩きも、少なくとも同じくらいはあるわけですから、この身分保障は、かなり危ういものになっています。つまり、1年間で10人くらいは裁判所を追われているわけですからね。大学、一般公務員はもちろん、大企業よりもはるかに危うい。ただ、やめても弁護士ができるというだけのことです。
出世に敏感なのは、第3章にも書いたとおり、そのように条件付けられ、それが習い性になって、自分を客観的に見詰める目を失ってしまっているからで、これも、行政官僚や一部の企業と何ら変わりません。というより、先輩の元裁判官たちにも、「霞ヶ関や大企業よりもさらに陰湿なのではないか?」と言っている人はかなりいますね。
--現在は刑事系裁判官が枢要ポストの相当部分を占めているようですが、これに対して民事系裁判官の反発はないのですか?
瀬木: 潜在的な反発は、ないではないのでしょう。しかし、本に書いたとおり、かつて裁判官支配、統制の形を完成させたといわれる矢口洪一長官時代に比べても、面従腹背の人すら少なく、上に対して見境なく尻尾を振る人が多いという嘆かわしい状況ではありますね。
また、これも本に書いていますが、刑事支配の一時期が重要ということではない。腐敗がはなはだしいからそのことを強調しましたが、やがてそれが終わっても、後に続くのは同様のメンタリティーの人たちなのであって、刑事支配の時代が終わったら何かが変わるという幻想を抱くべきではありません。現在の裁判所上層部は、矢口時代に比べても問題が大きく、それは刑事系に限ったことではないのです。
--第2章の最高裁判事の性格類型別分析が秀逸でした。詳しい説明はそれを読んでいただくとして、そのエッセンスを教えて下さいませんか?
瀬木: エッセンスと言われても難しいのですが(笑)・・・・・・。要するに、人間味のある人と怪物的な人が若干、ただし後者のほうが多い。残りの半分が純粋出世主義の俗物、半分が比較的知的だが本質的には型通りの官僚ということです。この二者の違いは、後者には少なくとも良心の片鱗はあるだろうということです。
--第1章、ブルーパージ、大規模な左派裁判官排除工作に、ある時点の裁判官出身最高裁判事の少なくとも半分が関与していたというのはショッキングでした。「法の番人」たる裁判官の、しかもそのトップのやることとは思えない。なぜ、このような人間がトップに昇り詰めるのでしょうか?
瀬木: この本でさまざまな側面から論証していますが、日本の裁判官は、実は、裁判官というより、法服を着た「役人」、裁判を行うというより事件を処理している制度のしもべ、囚人です。裁判官という職業名や洋画などからくる既成のイメージは捨てて下さい。
事実、本書第5章でも論じたとおり、トルストイは、短編『イヴァン・イリイチの死』において、帝政ロシアにおける官僚裁判官の本質を、非個性的で基盤の脆弱な浮動的インテリ、ないしは疑似インテリとして、きわめて的確にとらえています。まあ、天才だから大昔にそういうことができたのだとは思いますが、いずれにせよ、そういう曇りのない眼で本質をみて下さい。ブルーパージに貢献し、そのことを公言して恥じないような人物だからこそ、最高裁判事になれたのです。
--「司法制度改革」はうまくいったのでしょうか?
瀬木: 日本の改革の常ですが、問題の本質を見極めてそれに応じた改革を行うのではなく、「改革のための改革」になってしまった面があります。
成功したのは、たとえば法テラスのような公的な法的扶助、情報のネットワーク、これはいいです。
裁判所・裁判官制度については、本書のいくつかの章で詳しく分析したとおり、裁判所当局によって悪用された側面が大きく、そのために、たとえば裁判員制度についても、制度の趣旨がゆがめられています。被告人による選択制の制度とし、裁判員辞退事由をよりゆるやかに認め、守秘義務の対象も限定すべきです。また、早急に、選択制の陪審員制度に移行すべきです。これも、詳しくは書物第4章のとおりです。
法科大学院については、『民事訴訟の本質と諸相』に書きましたが、政治的な駆け引きなどもあって、絶対やってはいけない乱立を許し、司法試験合格者数よりも1学年の学生数がはるかに多いという状況でスタートさせてしまった。そんなことをすれば合格率が低くなるのは、小学生でもわかることです。はっきりいえば、官僚と政治家の責任が大きいと思います。司法試験合格者が一気に増える場合に従来の法学部教育ではたして十分かという問題はあり、その点では法科大学院制度に正当性はあるでしょう。ただし、資力のない家庭の学生が排除されないよう、優秀な学生については、奨学金や学費貸与、一部免除を、公的制度としても充実させていくべきだと思います。
--本書を読むと、裁判官には、決して友人にはしたくないタイプの人間が多いように感じます。典型的な裁判官像を教えていただけませんか?
瀬木: うーん、僕は、一貫して、少数派にはなったが良識派の裁判官も存在すると書いていますが、読んでみると、第2章、第5章などの印象が強いのでしょうね。
今年も、かなりの数の裁判官、ことに後輩から年賀状をもらっていて、書物が先のような印象を与えるとしたら、彼らにはすまないと思っています。ただ、ここ十数年の間に、裁判所の荒廃に伴い、問題の大きい裁判官が徐々に増えてきたという印象は否定できません。
典型的な裁判官像については、最高裁判事の類型からも推測できると思いますが、まあ、ごく普通の裁判官は、トップほど生臭くはないでしょう。しかし、血の重みがないというか、血が薄いというか、個人としての存在感に乏しい、感受性にもやや欠ける、鈍重な職人的役人が多数派になってきていることは、残念ながら間違いないと思います。
--裁判所のセクハラ、パワハラ等について、本書に記述されていることをも含めていかがでしょうか?
瀬木: これは、第5章の記述の中に含めざるをえないので書きましたが、あまり書きたくない部分ではありました。個人の問題もありますが、それ以上に裁判所という「精神的収容所」、「見えない檻」の中にいてストレスを被っている人間に不可避的に生じる問題という部分もあります。不祥事が2000年代以降に多発していることをみて下さい。裁判所の荒廃、退廃の影響は明らかだと思います。
また、大学に移って驚いたのは、各種ハラスメントについての対処がすごく進んでいることですね。比べると、裁判所はひどいです。表と裏の使い分け、二重基準(ダブル・スタンダード)の弊害もありますね。
--裁判所の自浄作用は働く可能性があるのでしょうか?
瀬木: もはやそれは難しいのではないかという認識が、この書物を書かせたということです。
「刑事の時代が終わればまたよくなるよ」などといった幻想は、学者にも根強いですからね。「おそらくそうではないですよ」ということは、かなり綿密に論証したつもりです。
--国政選挙における1票の格差問題などでは最高裁はかなり思い切った判断を出しているようにみえるのですが?
瀬木: そうした部分でも幻想が根強いですね。第4章を特に詳しくかつ綿密に書き込んだのは、そうした幻想を払拭するためです。
1票の格差判例における最高裁の論理は、国会に大きな裁量権がある、また、時間の面でも猶予を与えてあげるといった、政治家たちにものすごく配慮した内容なのですよ。アメリカの上院のように州の連合という国の成り立ちが根拠になっている場合には、各州平等に2人ということで、格差が出ても仕方がありません。しかし、日本で都道府県を単位にして選挙区を決めることに何の合理性、必然性があるのでしょうか?
英米における「1人1票の原則」は、せいぜい1対1.1とか1.2くらいまでを格差として許容するものだと思います。事実、アメリカ上院のような制度的な例外を除けば、そのような原則が貫徹していると思います。選挙権は、まさに人権の基盤ですから、それが当然ではないでしょうか?
メディアのみならず、憲法学者の中にさえ、衆議院1対2、参議院1対5などといった最高裁がガイドラインとしてきた数値を既定のものとして論じる傾向はありますが、英米法的常識からいけば、理解に苦しむものではないかと思います。
--最後に、裁判官になってよかったこと、悪かったことを、それぞれ教えていただけませんか?
瀬木: 僕は、最初から、社会科学・人文科学あるいは法学の学者になっていた可能性も高い人間なので、それとの比較になりますね。
社会・人文科学にいっていたらもしかしたらもっと独創的なことができたかもという気持ちはありますが、まあ、それはわかりませんからね(笑)。
法学者のほうは、可能性としてはかなりありましたね。法学部に進みましたから。
裁判官になってよかったと思うのは、やはり、人間、制度というものを長い間リアルに見詰められたということです。元々学者の眼をもっていましたから、平均的な裁判官とはかなり異なった眼で、裁判も、実務も、人間も見つめられた。鶴見俊輔氏にお会いして、プラグマティズムからも多くを学びましたし。書いてきた書物についても、やはり、このような体験に基づくところが大きいですね。
最初から学者になっていたら、理論をも制度をも、今ほど醒めた眼で客観的に分析することはできなかったでしょう。もちろん学者の言葉(ターム)にはより通じたに違いないですが、その利害得失は微妙で、学者の中にも、「最初から学者になっていたらもっとよかったのでは?」と言って下さる人と、「それだとかえって小さくまとまってしまったのでは?」と言って下さる人と、両方いますね(笑)。
それは、僕が決めることではなく、僕の学者生活、執筆生活が終わったあとで、人が決めることでしょう。僕としては、『民事訴訟の本質と諸相』のはしがきに書いたとおり、運命に従うだけです。基本的に唯物論者なのに運命論者なのですね。
いや、唯物論者というのも本当はどうなのか? 唯物論者が、『映画館の妖精』(騒人社)のようなファンタジーを書くかは疑問かもしれない。いずれにせよ、人生いろいろありましたから、運命論者になりました(笑)。
悪かったことは、本に書いたとおりです。が、それは、基本的に、もう過ぎ去ったことだと思いたいですね。もちろん、すべてが過ぎ去ることはありえませんが。
--それでは、これは質問ではなく、元裁判官の学者、そして、子どものころからの自由主義者、個人主義者(はしがき、あとがき)として、平均的な日本国民に対するアドバイスをいただけませんか?
瀬木: そうですね。これは司法に限りませんが、あとがきに書いたとおり、制度を、虚心に、客観的に、また、主体的に見詰める眼を養っていただきたいと思います。イデオロギーや教条によってではなく。何事もイデオロギーによってしか判断できない(奴らか俺たちか、ゼム・オア・アスの論理)、そして、自分を正当化するために、気に入らない者を批判、非難する、そうした正義派のやり方や言葉は、もはや行き詰まっており、その方向では、本当の変化は起こらないと思うからです。
僕は、クリスチャンではないのですが、新約聖書は若いころに何回も読んでいて、知恵に満ちた、深い書物だと思います。その言葉を借りれば、「蛇のごとくさとく、鳩のごとく素直に」自分の眼で見据えていただきたいと思いますね。
瀬木 比呂志(せぎ・ひろし)プロフィール
1954年名古屋市生まれ。東京大学法学部在学中に司法試験に合格。一九七九年以降裁判官として東京地裁、最高裁等に勤務、アメリカ留学。並行して研究、執筆や学会報告を行う。二〇一二年明治大学法科大学院専任教授に転身。民事訴訟法等の講義と関連の演習を担当。著書に、『民事訴訟の本質と諸相』、『民事保全法〔新訂版〕』(ともに日本評論社、後者は春ごろ刊)等多数の専門書の外、関根牧彦の筆名による『内的転向論』(思想の科学社)、『心を求めて』『映画館の妖精』(ともに騒人社)、『対話としての読書』(判例タイムズ社)があり、文学、音楽(ロック、クラシック、ジャズ等)、映画、漫画については、専門分野に準じて詳しい。
*日本国憲法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html


 Follow me on Twitter
Follow me on Twitter
Sorry, the comment form is closed at this time.