もうだいぶ前のことだが、配偶者に勧められてパトリック・ジュースキントの「香水~ある人殺しの物語~」という小説を読んだことがある。舞台は18世紀のフランスのパリ。町は汚濁と猥雑にまみれ、至るところに悪臭が立ちこめている。あまりにも不衛生で、貧しいヨーロッパの大衆の生活が見事に描写されていた小説だった。その後、この小説が映画化されたので見たが、主人公の出生シーンはなかなか衝撃的だった。腐った魚やらゴミやらが回りに悪臭を放っている下町のとある魚屋の女性が主人公:ジャン=バティスト・グルヌイユのヘソの緒を自身で、包丁で切り落とし、そのまま、ゴミ溜めに捨ててしまう場面を映画は忠実に再現していたからだ。
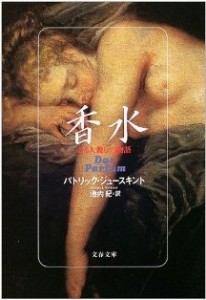
ところで、16世紀の「大航海時代」以降、アフリカ、アジア、北アメリカ、南アメリカの人たちから大規模な略奪を重ねたヨーロッパ人が、近現代史、200年の勝利者であったために西洋に対して、私たち日本人はあまりにも美しい誤解を巧みに植え付けられたまま、現在に至っているようだ。そろそろ冷静にありのままの事実を直視すべき時であろう。
以前のレポートでも紹介させていただいたが、ヨーロッパが200年にわたる略奪、殺戮をほしいままにしていた1820年においても、まだ、アジアの方が豊かだったのである!
1820年において中国、インド、東南アジア、朝鮮、日本からなるアジアの所得は、世界の58%を占めていた。その後、19世紀におけるヨーロッパの産業革命、20世紀に入ってアメリカの工業化が進むことによって、1950年には、ヨーロッパとイギリスとイギリスの4つの旧植民地(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)が世界所得の56%を占める一方、アジアのシェアは、19%までに落ち込んだ。ところが、この頃からアジアは成長し始め、1992年の段階で、39%までに回復。2025年には、57%に達し、200年ぶりにかつての地位を取り戻すことが予想されている。(「アジア経済論」原洋之介編NTT出版、「近代中国の国際的契機」東京大学出版会)
そこで今回は、21世紀の新しい時代に備えて私たち日本人が目を覚ますための本を紹介したい。「ものぐさ精神分析」という本で一世を風靡した岸田 秀氏の「日本がアメリカを赦す日」(毎日新聞社)である。有名な政治学者である京極純一氏がこの本の書評を書いていたので、まず初めに紹介させていただく、以下。
<歴史における正義とは何か>
著者の岸田秀先生は精神分析の専門家で著書が多い。このたび、「日本とアメリカの歴史の、これまたそのごく一部にほんのちょっぴり触れただけ」と謙遜(けんそん)する新著『日本がアメリカを赦(ゆる)す日』が毎日新聞社から出版された。読み易く、分かり易いことは、これまでの著書と同様で、ご一読をおすすめしたい。

表題が示すように、この本は、日米関係150年の歴史を資料に、日本人とアメリカ人の生活心理と相互交流の実際を、精神分析の角度から、的確に解説した、面白い読みものである。
この書物の冒頭、1853年、ペリー艦隊来航の後、「近代日本はアメリカの子分として出発しました。」と著者は説明する。その後の「日本は屈辱感、敗北感、劣等感に呻(うめ)きつづけてきました。その屈辱感から逃れるためには、日露戦争は日本民族の優秀さのゆえに勝ったのだという、この神話を是が非でも信じる必要がありました。のちの日米戦争惨敗の原因は、この神話です。」
ところで、日本の相手役であるアメリカ側は、「自分が相手のプライドを傷つけたことに鈍感で無神経です。自分以外の人間の行動におけるプライドという動機が見えません。」
その上、「近代日本は、外国を崇拝し憧憬する卑屈な外的自己と、外国を嫌い憎む誇大妄想的な内的自己に分裂して」いた。そして、日米お互いに相手の神経を逆撫でするとき、「アメリカは意識的、意図的に日本をイライラさせ、日本はつい気づかずにアメリカをイライラさせた。」「真珠湾奇襲に対するアメリカのすさまじい怒りは、アメリカ人の主観としては、恩知らずの裏切り者に対する善意の恩人の怒りでした。」「さらに深い理由、第一の根本的理由は、僕(著者)によれば、アメリカの歴史、インディアン虐殺の歴史にあります。アメリカ人は無意識的に日本人をインディアンと同一視していると考えられます。人間は自分が犯し、かつごまかした悪事と似たような悪事を他人が自分に対して犯すと、激しく非難するものです。罪悪感を外在化するためです。」「アメリカにとっても、日米戦争はやる必要のなかった戦争でした。」「日本は敗戦後から今に至るまでずうっとアメリカの属国で、その占領下にあります。」
「現在の日本人の平和主義は、平和主義でなく、降伏主義、敗北主義です。」「一種のマゾヒズムでしょうね。」「現状では、日本の平和主義は偽善でしかない。」
生活と文化については「一般性とか普遍性の面でアメリカ文化のほうが日本文化より上だ。」日本文化の基盤は「和」と「世間の眼」に基づく「一種の性善説」の人間観である。しかも、「言語化されていないため、外国人との関係を築くのが難しい。」「が、捨てることもできない。どこでも日本人ムラができる。」
アメリカは「おのれを普遍的正義の立場、善悪の絶対的判定者の立場におき、それに従わざるを得ないような無条件降伏に敵を追い込んでおいて、敵を裁くのが好き」である。
アメリカは「インディアン虐殺を正当化」する「正義の国」とされ、「強迫神経症の患者で、反復強迫の症状を呈している。」「今日の日本の繁栄は、インディアン・コンプレックスに苦しむアメリカ人の精神安定のために必要だったのです。」日本の繁栄は「アメリカ文化の普遍性の夢がついに実現した物語でした。」
アメリカと日本の社会と文化の特性をよく心得た解説書、実際生活の中で参考になる事柄の多い有用な手引書としておすすめしたい。
「毎日新聞2001年4月8日」(引用終わり)
ところで、著者の「アメリカの子分としての近代日本」という分析は、多くの日本人のプライドを傷つけるかもしれない。しかしながら、現実を冷徹に認識できなければ、現実を変える対処法を見つけることは、できないことを肝に銘じるべきだろう。特に日本は敗戦後から今に至るまですっとアメリカの属国で、その占領下にあることを冷静に認識していないと、米国から要求のあった集団自衛権、TPP等の問題を安易に捉えることになり、これから大変なことになるだろう。米国覇権に陰りが見える時代に入った今、読み返してみる価値は十分にある。もう、1冊は「嘘だらけのヨーロッパ製世界史」というこれも同じく岸田氏の本である。この本は、大論争を欧米に巻き起こした英国人歴史学者マーティン・バナールの「黒いアテナ」の解説を主に岸田氏が独自の見解を述べるユニークなものになっている。山川出版の世界史の教科書とあまりに内容がかけ離れていることに吃驚される方も多いと思われるが、著者は、現在、一般に流布している世界史は、西洋人が自分たちを優位に立たせるために作ったプロパガンダ、コマーシャルだと言っているのだから、全く立場が違うわけだ。

以下、本書から引用。(208ページ)
<ヨーロッパ中心主義の悪魔的魅力>
「アーリア主義を頂点とする、ヨーロッパ人しか文明をつくれないとか、ヨーロッパ文明は最高の普遍的文明であるとか、ヨーロッパ民族は世界を支配すべき優秀民族であるとかの近代ヨーロッパ中心主義の思想をヨーロッパ民族がつくった動機は、ほかの諸民族に対する嫉妬と劣等感である。隠蔽されているというか、あまり認識されていないようであるが、世界の各民族がそれぞれ主として自分たちの土地の産物で暮らしていた近代以前においては、土地が痩せていて気候条件にも恵まれなかった(もちろん、不利な条件はそれだけではなかったが)ヨーロッパ民族は世界の諸民族の中でいちばん貧しい民族であった。もうとっくに嘘がバレているが、いわゆる「未開人」が貧しく惨めな野蛮生活を送っていることを「発見」したのは、近代ヨーロッパ人の探検家たちであった。ところが、いわゆる「未開人」を貧しく惨めな生活に追い込んだのは近代ヨーロッパ人であって、そのような「発見」はこのことを隠すために必要だったのである。
近代ヨーロッパ人は、世界の情勢を知るにつれ、ますます他民族への嫉妬に駆られ、劣等感に苦しめられ、そして、貧しさに苛まれて、どこかほかにいいところがあるような気がして故郷のヨーロッパに安住できず、難民あるいは出稼ぎ人となって世界各地に押し出されてゆくようになった。そして追い詰められた者の強さで必死にがんばったのであった。ヨーロッパ中心主義の歴史観では、「大航海」時代のヨーロッパ人は、冒険心に富み、進取の精神に満ち溢れ、あらゆる危険をものともせず、未知の世界の果てまで余すところなく探求して飽きなかった勇敢な人たちだったことになっているらしいが、それは自己粉飾である。なかには、そういう者もごく一部いたかもしれないが、故郷のヨーロッパをあとにした者の大部分が飢餓や宗教的、人種的迫害から必死に逃れようとした難民であった。地球規模で言えば、近代はヨーロッパに大量の難民が発生した時代であった。故郷で何とか過不足なく暮らしてゆけている者がどうして故郷を捨てて見知らぬ土地へ逃げてゆきたいと思うであろうか。
その結果、必然的に、ヨーロッパ以外の世界の各地でヨーロッパ民族と他の諸民族とがぶつかることになった。ヨーロッパ民族と他の諸民族との争いは、貧しく惨めな家に生まれ、そのため、いじけて意地悪ですれっからしで疑い深く、せこい性格に育ち、争いの絶えない厳しい環境のなかで場数を踏んでいるために喧嘩が滅法強く、暴れん坊で、家にいたたまれず飛び出してきて帰るところのない餓鬼と、お金持ちの裕福な両親のもとに生まれ(自然に恵まれ)、可愛がられてのんびりした性格に育って、人の悪意というものをあまり知らず、のほほんとわが家で豊かに暮らしていたお坊ちゃん(中略)との争いであった。
勝負は初めから決まっていた。この争いの最も典型的な例は、十六世紀初め(1531~1533年)のスペイン王国のごろつきピサロとインカ帝国の皇帝アタウァルパとの争いであった。要するに、ヨーロッパ人と比べれば裕福に暮らしていた他の諸民族の多くは、無警戒だったということもあって、手もなくやられてしまったのであった。それ以来、貧富は逆転し、ヨーロッパ民族は世界の諸民族の中でいちばん豊かな民族となった。
そのときに、惨めで劣悪な過去を隠蔽し、立派な過去を捏造しようとするヨーロッパ人の大掛かりな企てが始まった。その結果できあがったのがヨーロッパ中心主義の思想であり、ヨーロッパ製世界史である。それは近代ヨーロッパ人の他の諸民族に対する嫉妬と劣等感に基づく何かに駆り立てられたような残忍さ(中略)、すでにヨーロッパ内の少数民族を相手に習得していた技術を応用した他の諸民族の支配と搾取を正当化し、それに伴う罪悪感をごまかすということを動機として形成された思想であった。
ローマ人から蛮族と呼ばれていた古代ヨーロッパを古代ギリシアにすり替え、あまり自慢にならない中世の「暗黒時代」をすっ飛ばし、近代ヨーロッパ文明を栄光ある古代ギリシア文明の直系の子孫とする歴史の捏造もこの思想の一環であった。それは、卑賤から身を起こして成り上がった一家が滅亡した昔の名家の系図を買い、過去を隠してその末裔と称するようなものであった。だから、「お家復興」というか、再生、すなわちルネサンスと称したのである。」 (引用終わり)

亡くなった小田実氏がマーティン・バナールの「黒いアテナ」の書評を書いているので、紹介する、以下。
『黒いアテナ』の鮮烈な主張
昔はよく現代のギリシア人が「黒い」のは、金髪、白い肌、長身、長脚のギリシア彫像の栄光の時代のあと、ギリシアの周囲の蛮族(英語のバーバリアンということばは、ギリシア語の「バルバロス」から来ている。すなわち、文明人のギリシア人の耳にはバルバルとしか聞こえないわけの判らないことばをしゃべる連中はそれだけで野蛮人だ。そういうことになった)と混交、混合し、さらには蛮族中の蛮族のトルコ人の支配を長期間にわたって受けたからだと言われたものだ。最近はそうでもなくなって、あれは昔からそうだったのだと言われるようになって来ていたが、それをまちがいなくそうだと強力に主張した一書が近年になって現れた。それが、この1987年に第1巻が世に出たマーティン・バナールの『黒いアテナ』だ。彼はそう証拠を集めて主張しただけではなかった。元来が本質的に「黒いアテナ」だったのを「白いアテナ」に変えたのは1785年に始まるドイツを中心とした「ヨーロッパ、西洋」の歴史の「偽造」だと、これもまた強力、鮮烈に主張した。
ギリシア語の語彙に見られる西セム系、エジプトのルーツ
この本のことをここで長々と説明するつもりはない。すべては『黒いアテナ』自体を読めば判ることだ。ただ、ここで私なりにまとめ上げた紹介を少し書いておけば、バナールは、今はアメリカ合州国のコーネル大学の教授だが(それともすでに引退しているかも知れない、それほどの年齢だ)、もともとはイギリスのケンブリッジ大学で中国学を勉強し、教えもしていたイギリス人の70歳に近い年の学者だ。若いときには、ベトナム反戦運動に参加し(そのころ、ひょっとしたら、私は彼に会っていたかも知れない)、同時に当時イギリスでは事実上何の研究もされていなかったベトナムを研究、日本史も勉強した。両者ともに、混合しながら、同時に独自に文明をつくり出していて、それはのちのギリシア研究のいい「モデル」になった(そう彼は『黒いアテナ』第1巻の「はしがき」で書いている)。
そのあと、同じ「はしがき」のなかでの彼自身のことばを引用して言えば、「世界の危険と興味の中心となる焦点はもはやアジアではなくて東地中海になった」と彼には見えて来て、そちらに研究対象を移し、ヘブライ語(彼には少しユダヤ人の血が入っている、そう彼は言う)、エジプト語を学び、さらにギリシア研究に至って、彼は重大な「発見」を二つする。ひとつは、ギリシア語の語彙の半分はインド・ヨーロッパ語系のものだが、あと25パーセントは西セム語系(ヘブライ語――古来のユダヤ人言語もそこに入る)、20―25パーセントはエジプト語だという「発見」だ。しかし、なぜかくも混交が起こったのか。それはかつて古代ギリシアがエジプトと西セム語系言語をもつ古来のユダヤ人の国フェニキアの植民地だったからだ――これがバナールの第二の「発見」だが、そうだとすれば、当然、古代ギリシアには、フェニキアのユダヤ人要素とともに、「黒い」アフリカの一部のエジプトもギリシアの構成要素のなかに入って、古代ギリシアは「白いアテナ」ではなくなり、「黒いアテナ」、そうとしか考えられないものになる。そうバナールは強力に主張する。
西欧による歴史の「偽造」
これだけでも大問題になって論争がまきおこって不思議はないが、もうひとつ、彼は重大な主張を、証拠を集めてやってのけた。それは、さっき述べた歴史の「偽造」である。それは大航海時代以来、侵略と植民地支配で世界の中心にのし上がって来た「ヨーロッパ、西洋」が、ことにそのなかで新興勢力のドイツが牽引力になって、近代になって自分たちの文明を古代ギリシアに始まるものとして、ここ200年のあいだに元来が「黒いアテナ」だったはずの古代ギリシアを、「白い」自分たちの先祖であるのにふさわしく「白い」アテナに「偽造」してのけたというのだ。この本の副題は「古典文明のアフロ・アジア的ルーツ」だが、その第1巻(これが1987年にまず出版された)にさらにもうひとつつけられた副題は「古代ギリシアの偽造 1785年―1985年」とまさに激しい。また、きびしい。
『黒いアテナ』をめぐる論争
これでこの本が「ヨーロッパ、西洋」で問題にならなかったら不思議である。案の定、大論争がまき起こり、それはまだ続いている。「聖書以来、東地中海についてのもっとも論議された本」と評した学者もいるし、「好むと好まざるとにかかわらず、バナールの事業は、ギリシア文明の起源と古代エジプトの役割についての次の世紀における認識を深いところで示している」と言った学者もいる。そして、この二つの発言を紹介しているのは『大学における異端』と題した、これまでの『黒いアテナ』にかかわっての論争を「肯定」「否定」あわせてまとめて紹介した本だが、こうした本が出版されていることだけでも、論争の規模の大きさと激しさが判るだろう。「賛否」両論半ばと言いたいが、マーティン・バナール自身が書いているように、「否」が「賛」より多いようだ。そして、「否」が古代ギリシア研究の専門家に多くて、「賛」は私自身をふくめて、この本をこれから読もうとしている読者のような専門家でない知識人――「知的大衆」に多いと、これもバナール自身が書いていた。
バナールによるパラダイム転換
こうした事態にあって、よく使われるのは、研究、本の質の理由だ。質が劣っているので、この研究、本はわが図書館には置かない――これがよく使われる理由だが、この質の問題でいつでも出て来るのは、専門家が見てどうかという問題だ。
私にはバナールの学識、あるいは、逆にバナールを「アマチュア」とこきおろすレフコビッツの「専門家」としての学識を判定する能力はないが、私にはバナールの学識、そして、研究それ自体は決して「アマチュア」程度のものとは思えない。しかし、たとえ、彼が「アマチュア」だとしても、バナール自身が主張するように、トロイの遺跡をみごとに発掘してみせたハインリッヒ・シュリーマンは言うに及ばず、クレタ線文字Bをギリシア語としてこれまたみごとに解読してみせたマイケル・ベントリスも偉大な「アマチュア」だった。シュリーマンの本業が企業家なら、ベントリスは建築家だ。
バナールは『黒いアテナ』第1巻の「序文」の冒頭に、科学における「パラダイム」転換の必要を説いたトーマス・クーンのことば、「新しいパラダイムの根本的な発案をなしとげる者は、たいてい常に、彼らがパラダイムを変えるその領域において非常に若いか、非常に新しいか、そのどちらかである」を引用したあと、中国研究を長年して来た自分が今『黒いアテナ』でしていることは、厳密な意味でのパラダイム転換ではないとしても、それと同じように根本的なことだと述べていた。私も彼のことばに同意する。
(引用終わり)
どう判断されるかは、別にしてあまりにも興味深い指摘である。
ここで、私たちが忘れてはならないのは、ジョージ・オーウェルの次のことばである。
「過去を支配する者は未来を支配する。そして現在を支配する者は過去を支配する」
(『一九八四年』)
*ところで、日本では宮司の三島敦雄氏が1927年に「天孫人種六千年史の研究」を刊行し、シュメル人と日本人を結び付ける歴史学説を唱えたことがある。この書は100万部近くの超ベストセラーになったが、1945年の敗戦後、GHQはこの本を一冊残らず探し出して没収、焼却した。ご存じだろうか。
このように歴史は勝者によって作られていくのである。



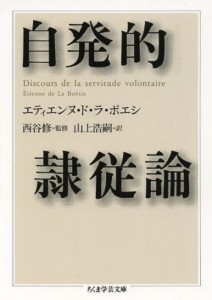
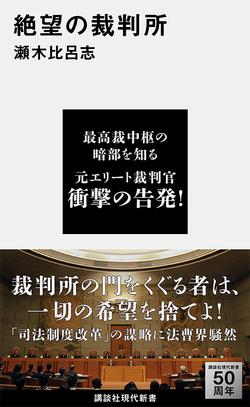

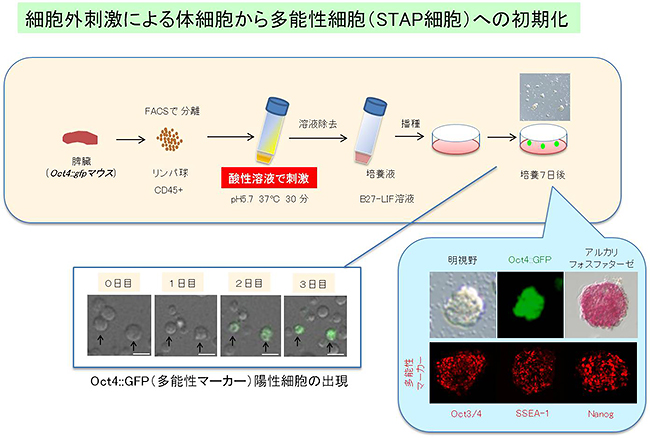
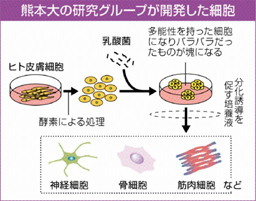




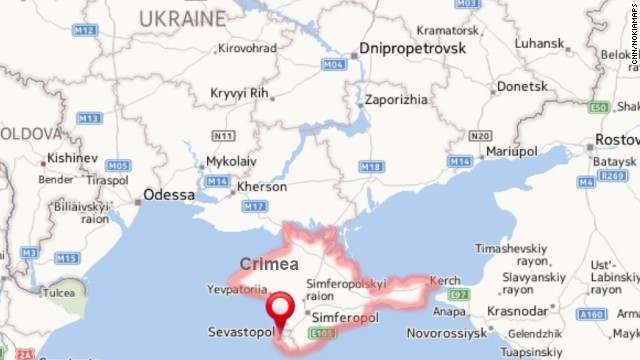
 Follow me on Twitter
Follow me on Twitter