成人式を迎えた若人に是非、読んでもらいたい本である。
今回は、如何に現代人が「グローバリズム、新自由主義の思想」に毒されているかを、また、日本では、公共を考える政治、国益(国民全体の利益)を守る政治が機能しなくなりつつあるかを理解できる逆説的な名著として、京都大学の人気講師の話題の本を紹介させていただく。
それでは、本の内容を要約して紹介する。
「僕は君たちに武器を配りたい」瀧本哲史著(講談社)
<第1章 勉強できてもコモディテイ(使い捨て商品)>
医師、弁護士、公認会計士といったような高学歴の・高スキルの人材が、世界中の先進国でニートやワーキングプアになってしまう潮流が押し寄せている。これまで、大学が伝統的に提供してきた、「知識をたくさん頭脳につめこんで専門家になれば、良い会社に入れて良い生活を送ることが可能となり、それで一生が安泰に過ごせる」というストーリーが世界規模で急激に崩れ去ろうとしている。
しかし、最近の日本では「勉強して努力すれば必ず幸せになれる」という考え方がメディア等で盛んに宣伝されている。自己啓発書が相次いで出版され、朝活などというものが盛んに開かれている。そうした努力神話を信じて、英語やITや会計を勉強した人のうち、実際に年収が増えた人はほとんどいない。
これは、学歴信仰が壊れ、経済のグローバル化が急ピッチで進み、日本人同士のみならず外国人との間でも職の奪い合い始まっている今日の日本が、明治維新以来の不安定な時代となっていることを意味している。
そういう時代だからこそ、ますます安定した道を求める真理も昂じて、「資格を取れば安心できる」とか勉強しなくてはならないといったストーリーに乗ることを欲したのだろう。それに乗じた形で勉強ブームといえる現象を起こし、金儲けをしている目先の利く人たちがいる。
いまの世の中、つまり高度に発達した資本主義(米国主導のグローバリズム)の下では、必死に勉強して「高度なスキル」を身につけてもワーキングプアになってしまう。それは、かつて高収入を得られた付加価値の高い職業が、もはや付加価値のない職業へと変わりつつあることに起因している。弁護士にしても、英会話が堪能にしても、MBA取得でも、需要と供給のバランスが崩れ、スキルや資格を持った者が余っている状態になってしまっている。
こうした急激な社会変化が、あらゆるところで起こっているのが現代の社会である。今まで、うまくいっていたやり方が通用しなくなり、これまでと同じ方向性で頑張っても、豊かな生活を営むのは難しくなってしまった。物心両面ともに幸福で充実した人生を過ごすには、これまでとはまったく違う要素が必要なのではないか。そのことにみな気づき始めているのだが、かといってどうすればいいのか分らない。それが今の時代を覆っている閉塞感の大きな一因だ。(本当は根本的な哲学、歴史観に基づくパラダイムシフトが必要なのだ)
留めることができない変化は、一部の例外を除いて、どんどん賃金の最低金額が下がっていく、ということだ。(日本政府と日本銀行が現在の政策を変更しない限りにおいて)
ここで瀧本先生は「コモディテイ」という概念を持ち出してくる。市場に回っている商品が、個性を失ってしまい、消費者にとってみればどのメーカーのどの商品を買っても大差がない状態。それを「コモディテイ化」と呼ぶ。経済学の定義によれば、コモディテイとはスペックが明確に定義できるもののことを指す。材質、重さ、大きさ、数量など、数値や言葉ではっきりと定義できるものは、すべてコモディテイだ。つまり、個性のないものはすべてコモディテイなのである。
一定のレベルを満たしていれば、製品の品質は関係ない。例えば、日本の自動車部品メーカーが作る製品の質は、非常に高いレベルにある。しかし、グローバル化して少しでも安い部品を調達したい自動車会社から見れば一定のスペックを満たしていれば、それらの部品はすべて同じだと判断される。だとすれば、少しでも価格の安い方から買いたい。だから、今の自動車業界、とくに部品を供給するビジネスは、どれほど品質が高くても買い叩かれる構造となっている。コモディテイ化した市場で商売をすることの最大の弊害は徹底的に買い叩かれることにある。
さて、ここで彼は主張する。コモディテイ化するのは商品だけでなく、労働市場における人材の評価においても、同じことが起きている。これまでの人材マーケットでは、資格とかTOEICの点数といった、客観的に数値で測定できる指標が重視されてきた。だが、そうした数値は、極端に言えば工業製品のスペックと何ら変わりがない。同じ数値であれば、企業側は安く使える方を採用するにきまっている。TOEIC900点以上ならだれでも同じということになっている。だから、コモディテイ化した人材市場でも、応募者の間で、どれだけ安い給料で働けるかという給料の値下げ競争が始まる。
こうしたコモディテイ化の潮流が、世界中のあらゆる産業で同時に進行している。その流れから逃れることは、グローバリズムに浸食される現代社会に生きる限り、誰にもできない。
これからの時代、すべての企業、個人にとって重要なのは、非常に難しいがコモディテイにならないようにすることなのだ。
労働者の給料がどんどん安くなってきているもう一つの大きな理由は、最低賃金の募集でも喜んで働く人がどんどん増えているということだ。このように、これからの日本では、単なる労働力として働く限り、コモディテイ化することは避けられない。
それでは、どうすればコモディテイ化の潮流から、逃れることができるのだろうか。人より勉強するとか、スキルや資格を身につけると言った努力だけでは意味をなさない。
答えは、スペシャリティになることだ。スベャリティとは、要するに「他の人には代えられない唯一の人物(とその仕事)オンリーワンになること」である。あらゆる業界、あらゆる商品、あらゆる働き方においてスペシャリティは存在する。
しかし、その地位は決して永続的なものではない。ある時期にスペシャリティであったとしても、時間の経過に伴い必ずその価値は減じていき、コモディテイへと転落していく。スペシャリティになるために必要なのは、これまでの枠組みの中で努力するのではなく、まず、最初に現在の超エリートが創ろうとしている資本主義の仕組みをよく理解して、どんな要素がコモディティとスペシャリティを分けるのか、それを熟知することだ。(*もちろん、一番効率的な方法は、超エリートのインサイダーになることである)
<第2章 「本物の資本主義?」が日本にやってきた>
戦後の日本は奇跡の復興とも呼ばれた経済成長を遂げた。そのころの日本企業を支えてきたのは、いわゆる「護送船団方式」と言われる政府の手厚い保護政策であった。事業の許認可や輸入品に対する厳しい規制を設けることで新規参入を妨げ、競争はあってもそれに敗れた大手企業からできるだけ落伍者を出さないよう、あらゆる分野で政府がコントロールしていた。
しかし、1985年のプラザ合意、そえから数年間の欧米資本によってつくらされたバブル崩壊と時を同じくして終焉する。為替操作による作られた円高と自国通貨建てで対外投資をすることを許されない状況下での経済グローバル化によって日本の国内産業は、生産拠点を海外に移すことを余儀なくされた。その結果、中国や台湾、シンガポールなどをはじめとした新興国の産業化が次々に進み、安い労働力で日本の産業から仕事を奪っていくように仕向けられた。世界中の人々と市場で競争を迫られる著者の言う「本物の資本主義」の社会へと否応なく足を踏み出さねばならなくなったのが現在の日本である。日本のような実際には主権のない国の企業はきわめて主権のある国と比較して不利な競争を強いられることになる。
国内需要の低迷で何とかしなければならなくなったとき、全社一丸となって踏ん張ればまた上向くということは、もはや絶対に期待できない。(*それができるのは、国だけである。しかし、マネーの帝国循環をさせるために、日本のその機能は米国によって封印されている。)部品メーカーも販売店もしのぎを削って、より効率を高めた企業がそうでない企業を呑み込んでいく、あるいは日本から海外への進出に対応できた事業者だけが生き残っていく、そういう時代なのだ。資本主義を支える根本的な原理が「より良いものが、より多く欲しい」「同じものなら、安いものの方がいい」という、人間の普遍的な欲望に基づいているからである。(*しかし、なぜその製品が安くなったのか、考えてみよう。政治力による為替操作によるかもしれないではないか。)
現代の日本の産業界で労働者の賃金が下がってきているのは、産業界が派遣という働き方を導入したのも原因の一つだが、本来は超過利潤を生む技術革新が国際政治における日本政府の力のなさをカバーするために賃金を下げる方向のみに使われたことにある。 その結果、自車産業に代表される工場のラインが最新鋭にオートメーション化され、コモディテイ化した労働者がそこに入っても、高品質の製品が作れるようになった。シュンペターの理論によれば、会社に超過利潤をもたらす技術革新が円高をカバーするために使われ、労働者の賃金を下げることによって生き延びる方法を企業にとらせたのである。たしかに産業の成熟化が進み、熟練労働者が必要なくなれば、労働者は必然的に買い叩かれる存在となっていくのであるが、国際政治というパワーポリティックスの中で半分しか主権のない国、日本はいつも不利な条件を受け入れさせられるのだ。白色人種でない敗戦国の特色だとも言えよう。
日本経済が疲弊化していった理由はほかにもある。国レベルで見ても、日本のビジネスモデルというのは、すでに陳腐化している。かつて日本が強かったのは「摺り合わせ製造業」という分野だった。しかし、時代が変わり、すさまじい工作機械(日本製であることは言うまでもない!)の進歩により、中国では人海戦術で多品種の製品を作るようになり、差をつけることが難しくなってしまったのである。現在でも日本の企業の作る品質は高い。しかし、中国の企業の製品の品質との差は微妙で、ユーザーにとっては殆ど関係がない。ユーザーにとっては「分らない差異は、差異ではない」のである。それより、色やデザイン、価格といったはっきり自分でわかる差異の方が大事なのである。
(*瀧本先生は中国を初めアジア諸国が日本の工作機械がなければ、生産できないことにはわざと触れていない。)
<第3章 学校では教えてくれない資本主義(グローバリズム)の現在>
起業については、卒業したての学生が起業するときに、一番よくある失敗は、コモディテイ会社を作ってしまうことだ。学生ベンチャーが業界に新規参入し、たまたまある時期成功したとしても、それは学生の労働力が社会人に比べれば圧倒的に安く済み、またヒマであるがゆえに仕事が速いと言った理由で、一時的に競争力があったに過ぎない。だからこそ学生は、卒業後すぐな起業するのではなく、一度就職して、社会の仕組みを理解した上で、コモディテイ化から抜け出すための出口を考えながら仕事をしなければならない。そうして出口を考えながら好機を待っていた人が、30前後で満を持して起業し、成功するパターンがベンチャーには多く見られる。
(専業主婦とは、夫に自分の人生のすべてをかけるということである。死ぬまで健康な男はいない。絶対に潰れない会社も存在しない。他人に自分の人生のリスクを100%委ねることほど、危険なことはない)
就職活動を控えた学生に、混乱をもたらしている原因のひとつとして、企業側が学生に求める資質の変化も挙げられるだろう。ほんの少し前までは、企業側は学生に対して即戦力であることを求めておらず、むしろ「真っ白な状態で入社したものを、一から鍛えたい」と考える企業が多かった。しかし現在では、どこの企業も入社後すぐに戦力として使える人材を求めている。1990年代までの日本は、高い最終学歴を獲得すれば、良い就職先に入ることができ、その後の人生における収入と社会的地位を確固とすることができた。学歴主義には弊害もあったが、少なくとも努力をして学校で成績を上げることが、社会的地位の向上につながるという、分りやすい価値観を社会と個人にもたらした。そのため、「良い暮らしができないのは個人の努力が足りないからだ」と、社会的にも見なされ、「なぜ私は不遇なのか→それは努力が足りなかった」という具合に、不公平感を抑えることができていた。その後、90年代後半、目に見える「テストの結果」や「学歴」に加え、「意欲」や「コミュニケイション力」などの定義があいまいで、個人の人格にまで関わるような能力が、評価の対象になり始めた。その結果、評価される側が、「何をどう努力していいか分らない」と混乱する結果を招いている。このような客観的に数値化できない、性格的特性を重視する傾向が広まることで、若者の無気力や諦め、社会へ出ることへの不安を助長してしまう可能性がある。
現在の日本で、安定した職場というはない。例えば1971年の就職人気企業を見ていると、潰れた会社、今青色吐息の会社が半数以上を占める。この40年間で日本を覆った規制緩和とグローバリゼーションの波に耐えられなかった会社は軒並み倒産するか、ビジネスそのものがコモディテイ化して苦境にあえいでいる。1971年の人気企業で現在生き残っているのは、グローバルブランド化した企業だ。
「世の中でこれが流行っているから」と現時点で話題になっている業界の会社に就職するのも、危険な選択と言える。更に言えば、現在絶好調な会社に就職することは、言葉を変えると、数年後にはほぼ間違いなく輝きを失っている会社に就職することとほとんど同義と言える。どんな素晴らしい企業も、未来永劫その価値を維持し続けることはできない。現代において、働く個人が常に経済的、社会的に高いポジションを維持するためには、次のどのビジネスモデルが成功するか潮流を見極めながら、転職を繰り返すことが必然の行動であることが分かる。投資の世界では「高すぎる株は買ってはいけない」というのが常識である。会社選びも同じだ。就職・転職希望者には、自分が就職を検討している会社が「高すぎる状態」になっていないか、よく考えてみるべきだ。
就職希望者に「これから伸びる産業はどこか」という質問を受けるが、すでに多くの人に注目されてしまっている分野には行かない方がいい、ということだ。就職先を考える上でのポイントは、「業界全体で何万人の雇用が生み出されるか」という大きな視点で考えるのではなくて、「今はニッチな市場だが、現時点では自分が飛び込めば、数年後に10倍か20倍の規模になっているかもしれない」というミクロな視点で考えることだ。 まだ世間の人が気づいていない市場にいち早く気付くことなのだ。
<第4章 日本人で生き残る4つのタイプと、生き残れない2つのタイプ>
資本主義社会の中で安い値段でこき使われず(コモディテイにならず)に、主体的に稼ぐ人間になるためには、次の6つのタイプのいずれかの人種になるのがもっとも近道となる。
1.商品を遠くに運んで売ることができる人(トレーダー)
2.自分の専門性を高めて、高いスキルによって仕事をする人(エキスパート)
3.商品に付加価値を付けて、市場に合わせて売ることができる人(マーケター)
4.まったく新しい仕組みをイノベーションできる人(イノベーター)
5.自分が起業家となり、みんなをマネージ(管理)してリーダーとして行動する人(リーダー)
6.投資家として市場に参加している人(インベスター)
だが、この6タイプの中でも、今後生き残っていくのが難しくなるタイプがいる。それは、最初のトレーダーとエキスパートだ。コモディテイ化が進む現在の社会では、これまでならば、様々な職場で求められ活躍できたタイプの人種が、どんどん必要とされなくなっていく。
トレーダーとは、単にモノを右から左に移動させることで利益を得てきた人のことを指す。会社から与えられた商品を、額に汗かいて販売している多くの営業マンがここに分類される。これまで個々の営業マン人間的能力と労力で培われてきた購買行動が、ネットにより瞬時に検索により、すべてのメーカーの同一ジャンルの製品が一覧で、スペックから価格まで比較検討できるようになった。消費者はその中から最も安いものを選んで買えばいい。企業においてもトレーダー的な業種、商社をはじめ広告代理店や旅行代理店のような商品を右から左に流すことで稼いでいた企業は経営が苦しくなってきている。
生き残りが難しくなってきているもう一つのタイプは、エキスパートだ。エキスパートとは専門家のことを指す。一つのジャンルに特化して、専門知識を積み重ねてきた人は、これまであらゆるジャンルで尊敬の対象だった。しかし、ここ10年間の産業のスピードの変化がこれまでと比較にならないほど早まってきて、産業構造の変化があまりに激しいために、せっかく積み重ねてきたスキルや知識自体が、あっという間に過去のものとなり、必要性がなくなってしまうのである。ある時期に特定の専門知識を身につけても、その先にあるニーズが社会変化に伴い消えると、知識の必要性が一気に消滅してしまうのである。
トレーダーとエキスパート、これまでのビジネスにおいて重要とされてきた「営業力」と「専門性」、その2つが実は風前の灯となっている。何かの分野でエキスパートであることや、モノを動かしてサヤを抜くという仕事は、かつての生産性革命の時代や、国家間での貿易で儲けていた時代にはヒーローでいられた。しかし、今現在の「付加価値を生む差異があっという間に差異でなくなり、コモディテイ化した人材の値段がどんどん安くなっている時代」には、時代遅れの人々にならざるを得ないのである。
<第5章 企業の浮沈のカギを握る「マーケター」という働き方>
これかに生き残るビジネスパーソンのタイプは、マーケター、イノベーター、リーダー、投資家の4種類だ。ただし、便宜上4つのタイプに分類しているが、ここでは一つのタイプを突き詰めるのではなくて、望ましいのは、人釣りのビジネスパーソンが状況に応じて、この4つの顔を使い分け、仕事に応じて、時にはマーケターとして振る舞い、ある機会には投資家として活動していく。そのような働き方が、これからのビジネスパーソンに求められる。
まず、マーケターとは端的、顧客の需要を満たすことができる人のことだ。大切なのは、顧客自体を再定義するということである。つまり、人々の新しいライフスタイルや、新たに生まれてきた文化的な潮流を見つけられる人のことを指す。自分自身で何か画期的なアイディアを持っている必要はない。重要なのは、世の中で新たに始まりつつある、微かな動きを感じ取る感度のよさと、何故そういう動きが生じてきたのかを正確に推理できる、分析力である。さらに売るものは同じでも、「ストーリー」や「ブランド」といった一見捉えどころのない、ふわふわした付加価値や違いを作れることだ。
そもそも資本主義社会では、仕組みとしてあらゆる商品がコモディテイ化していくことが宿命づけられている。ある企業が何か革新的な商品を開発しても、すぐに別の会社がより安いコストで同じような商品を開発しても、すぐ別の会社がより安いコストで同じような商品を作り出し、市場に投入して来る。資本主義社会の中では、常に市場の中で競争が行われ続け、コモディテイ化した商品はどんどん価格が下がっていき、やがて市場から淘汰されていく。陳腐化した商品しか作れない会社もまた勢いが衰え、市場からの退場を余儀なくされる。その繰り返しで、戦後の日本も発展してきたのである。ということは、企業が衰退を避けるには、イノベーションを繰り返して、商品の差異を作り続けなければいけない、ということだ。あらゆる業種、業態の企業が、その前向きな努力をすることで、全体としての社会が進歩していくのが、資本主義社会の基本的なメカニズムなのである。
しかし、インターネットが登場してきた以降の現代では、情報の流通コストがほぼゼロとなった。そのため「差異」は生まれた瞬間から、世界中に拡散し、模倣され、同質化していくこととなった。この十数年、企業の栄枯盛衰のサイクルが、かつてないほど速まっているのは、それが大きな利用である。この流れに巻き込まれているのは、大企業と言えども、例外ではない。企業のコモディテイ化が進む中で、唯一富を生み出す時代のキーワードは、「差異」である。「差異」とは、デザインやブランドや会社や商品が持つ「ストーリー」と言い換えてもいい。
わずかな「差異」がとてつもない違いを生む時代となったのだ。マーケターとは、「差異」=「ストーリー」を生み出し、あるいは発見して、もっとも適切な市場を選んで商品を売る戦略を考えられる人間だと言える。
<第6章 イノベーター=起業家をめざせ>
日本はこれまで人口は増える一方で、経済自体の規模が膨張していく時代が長く続いていた。成長のベクトルは常に上を向いており、あらゆる業種、業界に目指すべき成功のゴールが存在していた。がむしゃらに、愚直に、ひとつのことだけをやっていれば、幸せになれる時代があった。松下幸之助の言葉にあるような「成功するまで続ければ誰でも成功することができる」ということが現実にあった。しかし、現代では新興国をはじめとして世界中のあらゆるところでものづくりが行われており、高コストの日本の企業が愚直に生産を続ければ、それは「死への行進」に他ならない。
もし、日々行っている業務が「死の行進」だと感じたならば、とりあえず死の行進を続ける振りをして、自社の弱点を冷静に分析することをすすめる。自分が働いている業界について、どんな構造でビジネスが働いており、カネとモノの流れがどうなっていて、キーパーソンが誰で、何が効率化を妨げているのか、徹底的に研究するのである。そうして自分が働く業界について表も裏も知り尽くすことが、自分の唯一性を高め、スペシャリティへの道を開いていく。そして常日頃から意識して、業界のあらゆる動向に気を配ることで、「イノベーション」を生み出すきっかけと出会うことができる。
イノベーター的な観点からすれば、「落ち込んでいる業界にこそ、イノベーションのチャンスが眠っている」と考えていい。また、起業家が新しいビジネスを見つける時の視点として、「しょぼい競合がいるマーケットを狙え」という鉄則がある。今現在、凋落しつつある大手企業の周辺には、たくさんのビジネスチャンスが眠っている。イノベーター的な視点から学生に就職先をアドバイスするならば、「今落ち込んでいる業界の周辺企業で、将来的にナンバーワンのポジションを取れそうな会社を狙え」ということになるだろう。そのようにイノベーター的な考え方をすると、潰れそうな会社に入ることにも大きな意味がある。例えば、今はなんとか持っていても、将来の先行きはないだろうと思われる会社に入り、その会社を徹底的に研究する。そして、その会社が潰れる前に退職し、その会社を叩き潰す会社を作るのである。
イノベーションを生み出す発想力、特殊な才能の持ち主のみが持っている限られたものではない。イノベーションは、日本では技術革新と訳されるが、実は新結合という言葉が一番この言葉の本質を捉えた訳語だと考えている。既存のものを、今までとは違う組み合わせ方で提示すること。それがイノベーションの本質だ。社会にインパクトを与える商品やサービスを生み出したい、と考えたとしてもまったく新しい製品を作る必要はない。今既にあるものの組み合わせを変える、見方を変えることによってイノベーションを起こすことができる。
だからイノベーター型の起業家を目指すのであれば、特定分野の専門家になるよりも、色々な専門技術を知ってその組み合わせを考えられる人間になることの方が大切なのである。他の業界、他の国、他の時代に行われていることで、「これはよい」というアイディアは徹底的にパクれば、よいのである。イノベーションをある業界で起こすための発想術は、実はそれほど難しいことではない。その業界で「常識」とされてきたことを書き出し、悉くその反対のことを検討してみればよい。
<第7章 実はクレイジーなリーダーたち>
人間をマネジメントするスキルに必要なこととして、世の中に傑出した人物などほとんどいない。世のほとんどの人は凡人なのだから、その凡人をうまく使うスキルを学ぶことが大切なのである。リーダーには優秀だが我が儘な人をマネージするスキルも大切だが、優秀ではない人をマネージする人をマネージするスキルの方が重要なのである。ダメなところが多々ある人材に、あまり高い給料を払わずとも、モチベーション高く仕事をしてもらうように持っていくのが本当のマネジメント力なのだ。
<第8章 投資家として生きる本当の意味>
資本主義社会では、究極的には全ての人間は、投資家になるか、投資家に雇われるか、どちらかの道を選ばざるを得ないからだ。株を自ら所有するしないにかかわらず、私たちの社会は株主(資本家)なしには存続できない。我々が普段食べる食事も、移動するために乗る自動車も、毎日を過ごす家も、そのほとんどが民間企業、つまり株式会社が提供している。また自分が勤める職場も株式会社であるならば、その時点で自分という労働力を株主に提供することで、その見返りに報酬を得ているということになる。資本主義の国で生きる以上、株主(投資家)に意思のもとに生きざるを得ない、ということなのだ。それならば、自分自身が投資家として積極的にこの資本主義に参加したほうがいい。投資家に振り回されるのではなく、投資家たちの考えを読み、自らが投資家として振る舞うのである。そうすると、この世界が違って見える。
投資家として生きる上で必要なのが、「リスク」と「リターン」をきちんと把握することである。成功している投資家でも、すべての投資が成功しているわけではない。しかし、失敗が少ないのも、投資家のリスクの採り方としては、好ましくない。例えば、シリコンバレーの投資家たちはリスクを回避することよりも、リスクを見込んでも投資機会を増やすことを重視する。それはなぜか、投資という行為には、何よりも「分母」が大切だからだ。一つの案件にだけ投資するのは、カジノのルーレットで1か所だけにチップを置くようなもので、重要なのは、できるだけたくさん張ることなのだ。トータルで成績をあげたいと思えば、リスクを恐れずに積極的に投資機会を持たねばならない。失敗を怖がって、確実に儲かる案件だけに投資することは、結果的に自分が得られたかもしれない利益を遺失することにつながるのである。つまり、投資家として生きるならば、人生のあらゆる局面において、「ハイリスク・ハイリターン」の投資機会をなるべくたくさん持つことが重要となる。
そのような投資家的な生き方をするうえでは、投資の機会はできる限り増やすのが望ましい。ただし注意すべき点がある。それは「自分で管理できる範囲でリスクを取れ」ということだ。投資家がリスクを取るときは、必ず計算管理可能なリスクの範囲内で投資を行う。その観点からは、就職して一生サラリーマンの道を選ぶというのはハイリスクな選択である。サラリーマンは、他人にリスクを預けて管理されている存在なのだ。 つまり、自分でリスクを管理できない状態にある。大学を出て新卒で会社に入り、定年の60歳まで働いたとすると38年間を会社で過ごすことになる。しかし、近年では会社の寿命はどんどん短くなってきている。だからこそ、一つの会社に自分人生の全てを委託するのは非常に高リスクなのである。(紹介終わり)
<解 説>
如何だろうか。こんなにハードルの高い社会で普通の人が幸せに暮らせるのだろうか。
利益社会の極限化は何れ、共同体社会を破壊し、人間の社会生活そのものを成り立たなくさせてしまうだろう。この本の著者はそのことに気がついていない脳天気な人だ。
また、全く触れていないが日本では政治というものが全く機能しない(国家主権がない)ことが彼には当然の前提となっている。
それでは、誰がこんな社会を目指しているのか。世界の資本を独占するエリートたちが、自分たちの利益独占のためにそう言った社会を作ろうとしているのである。
一部の人たちは、この理念を「ニューワールドオーダー:新世界秩序」と呼んでいる。

グローバリズムの本国、米国では国際金融資本が経営する「多国籍企業」が犇めいている。
これらがすべてNFTC:全国貿易協議会という組織に集結して、ロビー活動を通して米国政権に圧力をかけ、現在だったら、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)という形で日本経済から富を収奪しようと目論んでいる。現在の米国は生き残るために日本という金の卵を産む鳥を貪り食おうとする位、分別をなくしている状態である。
確かに、ひとつひとつの企業を見ると、そのことを理解することは難しい。
「TPPは日本社会を破壊する!」と言う日本人も、マクドナルドでハンバーガーを食べ、コカコーラやペプシを飲み、家に帰ってマイクロソフトのOSの入ったインテル製PCを使って(自己情報の流失に対して)無防備にインターネットを楽しんでいる。
しかし、「マクドナルド、コカコーラ、ペプシ、インテル、マイクロソフト」は、すべてNFTC(全国貿易協議会)を通して、TPPを日本に押し付けてようとしている企業群であることに注目すべきであろう。
もうこれらの企業は十分日本に浸透しているのだから、これ以上何を望んでいるのかというと、まだ日本に入りきれていない仲間の多国籍企業を侵出させるためだ。
TPPというと真っ先に問題になるのが「農業」だが、NFTC(全国貿易協議会)のメンバーである世界最大の穀物商社「カーギル」や遺伝子組換えの「モンサント」「ダウ・ケミカル」はまだ入り込めていない。なぜなら、日本が関税を敷いて自国農業を守っているからだ。NFTC(全国貿易協議会)はそれが邪魔だと考えている。そして、その関税を「完全撤廃」させるのがTPPの目的である。
当然そうなれば、日本の農業は壊滅状態になる可能性もあるし、それを防御しようとすれば訴えられてISD条項の元に「損害を弁済させられる」羽目になるのがTPPだ。
ご存じのように経団連の米倉氏(住友化学)はTPP推進に邁進している。
彼の真意はどこにあるのか。
住友化学は、遺伝子組み換え農産物で知られる米国モンサント社と昨年10月に遺伝子組み換え農産物の種子と、強力な除草剤に関する契約を結んでいる。彼がTPPを推進するのは自社の利益追求のためである。ところで、モンサント社はベトナム戦争での枯葉剤を製造した会社である。枯葉剤を散布されたベトナムの地は長い間不毛の大地となり、定住の農民に塗炭の苦しみを味わさせたことを思い出す必要があるかもしれない。
NFTC(全国貿易協議会)のメンバーの中には「アボット・ラボラトリー」「イーライ・リリー」「ファイザー」「メルク」等の巨大製薬会社も混じっている。彼らは特許を盾にしてジェネリック薬を許可しないので、ジェネリック薬を推進している厚生労働省が懸念する医療費の高騰が起こる可能性もある。
もちろん、これも抵抗すればISD条項の元に「損害を弁済させられる」だろう。
訴訟はアメリカの弁護士が行うが、NFTC(全国貿易協議会)には「U.S. Chamber of Commerce(米国商工会議所)」という何の変哲もない名前のロビー団体が含まれている。
知る人ぞ知る米国でも最大のロビー団体のひとつである。
ここに多くの弁護団体が加盟しており、アメリカ式の訴訟を日本で行い、日本人から少しでも多くの金を毟り取りたいと考えているのである。訴訟大国を担う弁護団が入ってくるのであれば、今まで何でも「穏便」に済ませていた日本という国がなくなり、ブレンジスキーが言う見事な「アメリッポン」の完成になることだろう。
つまり、日本に入り込みたいが入れないアメリカの多国籍企業が山ほどあり、そのために、邪魔な日本政府(霞ヶ関))と関税を無力化させるために、NFTC(全国貿易協議会)はアメリカ政府を動かしてTPPという罠を仕掛けてきたのである。
もっともその先には、日本の公的文書を英語に、公用語を英語にする遠大な計画さえあるのかもしれない。欧米の超エリートは、前から指摘させていただいているように腹の底では「日本人が自発的に日本人でなくなる道をとるなら、それは日本民族の集団自殺であるが、それでも良い。だが、もしも日本人がその歴史的民族的伝統を復活させるようなことが、あれば我々キリスト教、ユダヤ財閥、フリーメーソン連合はただちに日本を包囲して今度こそ、日本民族を一人残らず、皆殺しにする作戦を発動するであろう。」と今でも腹の底で考えているからである。
もちろん、言語や文化が統一すれば、多国籍企業には非常に有利になる。それによって「情報のアクセスが増える」「乗っ取りがしやすくなる」「コストが削減できる」「文化を画一化できる」等の大きなメリットを作り出すことができるからだ。
「コスト削減」については、説明書や製品を現地語にローカライズさせる手間が省けることを考えてもよく分かる。また、NFTC(全国貿易協議会)には「米国出版社協会」やマグロウヒルが含まれているが、これはアメリカのほぼすべての出版物を扱う協会だ。
日本の文化を破壊させて日本語を諦めさせ、日本人全員を英語で読み書きするようにすれば、1億人のマーケットを新たに生み出すことさえ可能である。
世界の超エリートはワン・ワールドによる利益を追求しようとしている!
言語が画一化されれば英語のメディアがそのまま世界中に売れる。味覚が画一化されれば、マクドナルドもコカコーラもペプシも世界中に売れる。美的感覚が画一化されればGAPもリーバイスも世界中に売れる。グローバル化とは人間をレンガのように画一化し、アトム化する仕組みだ。
たとえば、マクドナルドは世界中の誰も知らない者はいない企業だ。そして、時価総額8兆円の超巨大多国籍企業でもある。
現在、世界各国の政府が弱体化(政治が機能不全になるように仕向ける)していく流れが世界のエリートによって意図的に作り出されている。そして、ユーロや、FTAや、TPPや、NAFTA(北米自由貿易協定)のように、第二次世界大戦前のごときブロック経済が再び作られようとしている。彼らは着々と戦争経済への布石も打っているのである。
彼らは最終的には、自分たちの利益のために
・世界を画一化し、ワン・ワールドにしたい。
・各国の通貨を消滅させ、世界通貨を一つにしたい。
・言語を統一化することによって支配を単純にしたい。
・文化を画一化し、価値観を一つにしたい。と考えている。
人間の本性に逆らうこの動きがいつまで続くかわからないが、現在、実際に多くの国の政治に一番大きな影響力をウラで行使しているのは、実は政治家でも官僚でも何でもない、多国籍企業を所有している国際金融資本家である。
もし、このような動きが完全に成功し、「アメリッポン」が完成したときには、そこに住む日本人は、この本に書いてあるように行動する他、生きる道はなくなる。
このまま外国資本に実質支配されている既存のマスコミ報道に日本の多くの方が誘導され続ければ、騙され続ければ、ごく一部の人以外、幸せに暮らせない「日本人が日本人であることを失った未来」が待っているのではないか。
確かにこの本に書いてある一つ一つのエピソードは興味深い。ただ、日本最高学府である京都大学のこの先生の日本人としての志の低さに呆れてしまう他ない。日本社会全体、世界全体をよくする思いなど彼にはこれっぽっちもないのである。
考えてみれば、米国のエリートによる日本人への洗脳はここまで及んでいることを心ある人は知るべきであろう。
<参考資料>
ユニクロの「英語公用語化」は第一歩に過ぎぬと大前研一氏
2010.10.03
今、日本で最もアグレッシブな経営を展開する企業の筆頭は、「ユニクロ」ブランドを擁するファーストリテイリングだろう。グローバル化を目指し、「英語の社内公用語化」でも注目を集めているが、それにはどんな意味があるのか、大前研一氏が分析する。会社をグローバル化するにあたってのユニクロの課題は「人材」だ。この点では、同業のスペインのZARA、スウェーデンのH&M、アメリカのGAPが有利である。彼らはみんな、国籍や人種によらないシステムを持っている。
それに対してユニクロは、外国人の採用を2010年度は全世界で300人、2011年度は同700人、2012年度は同1200人と徐々に増やしていく予定だという。店長以上の役職にある社員は今後、国籍に関係なく世界中の店舗に赴任することになり、そのために2012年3月から社内会議や文書で使う言葉を英語に統一する「英語の社内公用語化」の方針を打ち出している。
しかし、外国人の採用を増やしたり、店長経験者を海外に派遣したり、英語を社内公用語化したりするだけでは、まだグローバル企業とは呼べない。会社の組織を日本の本社を頂点としたピラミッド・ストラクチャーではなく、フラット化しなければならないのだ。
逆に言えば、グローバル企業において一番いけないのは「マウント・オリンポス・メンタリティ」である。つまり、オリンポス山の神殿(本社)から神様が下々にお告げを出すというやり方だと、世界中の様々な国籍の人々が混ざっている組織は、絶対にうまく動かないのだ。優秀な人は、オリンポス山の神殿にひれ伏さないからである。それぞれの店舗がすべて世界の中心であり、お客様こそが神様です、という「始めに現場ありき」のメンタリティが必要なのだ。
そしてそのためには、組織構造を完全にフラットなネットワーク型にするとともに、人の採用・評価・報奨・昇進システムを国籍や人種によらないフェアなものにしなければならないのである。これは「言うは易く、行なうは難し」だ。
ユニリーバやネスレなどグローバル企業の歩みを見ると、多国籍化が完成するまでには最低でも20年かかっている。そういう意味では、ユニクロはまだ、グローバル化に向けて第一歩を踏み出したに過ぎないのである。
(SAPIO2010年10月13・20日号)




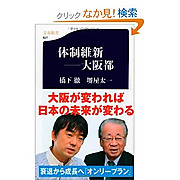

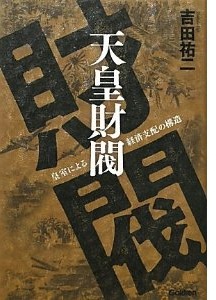


 Follow me on Twitter
Follow me on Twitter