*今回は本の紹介です。 「自滅するアメリカ帝国~日本よ、独立せよ~」
伊藤 貫(いとう かん、1953年(昭和28年) – )
日本の評論家、国際政治・米国金融アナリスト。東京都出身。東京大学経済学部卒業。コーネル大学で米国政治史・国際関係論を学んだ。その後、ワシントンD.C.のビジネス・コンサルティング会社で国際政治・米国金融アナリストとして勤務。アメリカワシントンD.C.在住。

<目 次>
まえがき 日本よ、目覚めよ
第1章 自国は神話化、敵国は悪魔化
第2章 驕れる一極覇権戦略
第3章 米国の「新外交理論」を論破する
第4章 非正規的戦争に直面する帝国
第5章 アメリカ人の“ミリテク・フェチ”現象
第6章 世界は多極化する—中・印・露の台頭
第7章 パックス・アメリカーナは終わった
終章 依存主義から脱却せよ
以前、アメリカ帝国の時代が終わることを予見したフランスの碩学、エマニュエル・トッド氏の「帝国以後」という本を紹介させていただいたことがある。以下。
「NHK衛星放送で再放送された「未来への提言」で取り上げられていた2002年9月に出版されたエマニュエル・トッドの「帝国以後」。
1976年にその著書「最後の転落」で乳児死亡率の上昇を根拠にソビエト連邦の崩壊を独特の視点で見事に予言したトッドは、この著書のなかで、幾分、遠慮がちにアメリカ帝国の崩壊は2050年までに起こると予想している。
おそらく、我々は、この控えめな言葉とは、裏腹にアメリカ帝国の崩壊を10年以内に、早ければ数年以内に目の当たりにすることになるのではないかと思われる。
戦後、あまりにも長く米国の巧みなプロパガンダによって、ある意味洗脳されてしまっている日本人には理解しにくいことであろうが、
その意味でもエマニュエル・トッドの「帝国以後」は21世紀の日本の未来に心を痛めている人々の必読の書と言えるかもしれない。
さすが、トッドはヨーロッパ、フランスの知識人である。冷徹にアメリカに対して何の思い入れもなく、その覇権構造を分析している。また、我々が住む日本という国がどのようにその覇権を支えさせられているかを冷ややかに観察している。
トッドは、単純な経済力や軍事力の分析、宗教やイデオロギーの対立のみに分析の軸足を置いていない。もちろん世界を評価するとき、それらの変数は分析にとって欠かせないものに違いない。従来の伝統的な方法に加えて、人類学者トッドの視野は「識字率」と「出産率」、すなわち教育と人口動態を、そのうえ過去から民族が受け継いできた「家族制度」と「婚姻形態」を、差異ある歴史の理解に不可欠な独立変数として認識する。このことによって、民主主義と自由主義の発展、およびその逆転としての文化的階層分化による民主主義の衰退=寡頭政治の台頭という現代世界の主要な潮流を明らかにし、人々を途方に暮れさせる世界の暴力的な混沌と行く末に迫っている。
『(…)世界中での成長率の低下や、貧しい国でも豊かな国でも不平等が強まっていることが把握できる。これは経済と金融のグローバリゼーションに結びついた現象で、論理的かつ単純に自由貿易から派生するものである。(…)しかし左のであれ右のであれ、マルクス主義のであれ新自由主義のであれ、単純すぎる経済主義に身を委ねることを拒むなら、厖大な統計資料のお陰で、現在の世界におけるすばらしい文化的前進がどれほどのものなのかを把握することができる。それは二つの基本的パラメーター、すなわち大衆識字化の全般化と、受胎調節の普及を通して表現される。(p50)
実例とその展開はいくらでも示すことができるだろう。ここで重要なのは、近代化過程が始まる以前の空間と農民習慣の中に組み込まれていた当初の人類学的様態を知覚することである。さまざまの家族的価値を担う地域と民族が、その時期その速度もさまざまに、次から次へと同じ伝統離脱の動きの中に引きずり込まれていった。農民世界の元々の家族的多様性は人類学的変数であり、識字化過程の普遍性は歴史的変数ということになるが、この両者を同時に把握するなら、われわれは歴史の意味=方向と多様性という分岐現象とを同時に考えることができるのである。(p82) 』
ソ連邦崩壊後のロシアと東ヨーロッパの旧人民共和国、フランスとドイツを中心とするEU諸国、日本、中国、中南米、アフリカ、さらにイスラム圏を含めて、地域的に差異のある民主主義と自由主義の発展をトッドは確信するのだが、現在のアメリカ帝国に対する評価は、極めて厳しく、帝国が崩壊過程に入っていると断言している。
『 1950年から1990年までの世界の非共産化部分に対するアメリカの覇権は、ほとんど帝国の名に値するものであった。(…)
共産主義の崩壊は、依存の過程を劇的に加速化することとなった。1990年から2000年の間に、アメリカの貿易赤字は、1000億ドルから4500億ドルに増加した。その対外勘定の均衡をとるために、アメリカはそれと同額の外国資本の流入を必要とする。この第三千年紀開幕にあたって、アメリカ合衆国は自分の生産だけでは生きて行けなくなっていたのである。教育的・人口学的・民主主義的安定化の進行によって、世界がアメリカなしで生きられることを発見しつつあるその時に、アメリカは世界なしでは生きられないことに気づきつつある。(p37-38)
どのようにして、どの程度の早さで、ヨーロッパ、日本、その他の投資家たちが身ぐるみ剥がされるかは、まだ、わからないが、早晩身ぐるみ剥がされることは間違いない。最も考えられるのは、前代未聞の規模の証券パニックに続いてドル崩壊が起こるという連鎖反応で、その結果は、アメリカ合衆国の「帝国」としての経済的地位に終止符を打つことになろう。P143
アングロ・サクソンの世界への関わり方は、不安定で流動的である。彼らの頭の中には、普遍主義的民族にはない人類学的境界線が存在する。その点で彼らは差異主義的諸民族に近いのだが、ただしその境界線は移動することがある。(…)
アメリカ合衆国の歴史も、この境界線の変動という主題をめぐる試みとして読むことができる。それによって中心集団は、独立から1965年までは連続して拡大し続けたが、1965年から今日に至るまで、縮小の傾向にある。(…)
ロシアは、おそらくフランス革命以来最も普遍主義的なイデオロギーに違いない共産主義を作り出し、世界に押し付けようとした。(…)
冷戦の間、アメリカはこの恐ろしい潜在力に立ち向かわなければならなかった。外に対しても内においても、である。(…)
共産主義というライバルの崩壊に対応する最近の数年間は、アメリカの普遍主義の後退が見られる。(p152-155)
アメリカ流の一方的な行動様式と呼ばれるものは、(…)その基本的帰結は、アメリカ合衆国が帝国というものに不可欠のイデオロギー手段を失ったということである。人類と諸国民についての同質的把握を失ったアメリカは、あまりにも広大で多様な世界に君臨することはできない。(p170-171)
ロシアの崩壊の結果、アメリカ合衆国は唯一の軍事大国となった。それと平行して金融のグローバリゼーションが加速する。1990年から1997年までの間にアメリカと世界全体の間の資本移動の差額の黒字は600億ドルから2710億ドルに増大した。これによってアメリカは生産によって補填されない追加消費に身を任せることができたのである。(p179-180)
アメリカ外交の酔っ払いの千鳥足のような行動振りには、一つの論理が隠されている。すなわち現実のアメリカは軍事的小国以外のものと対決するには弱すぎる、ということである。すべての二流の役者たちを挑発すれば、アメリカは少なくとも世界の檜舞台での役割を主張することができる。経済的に世界に依存しているという事態は、実際、何らかの全世界的なプレゼンスを必要とせざるを得ない。(p185-186) 』
トッドは、冷静な目で経済的に、軍事的に、自由と民主主義などイデオロギー的に、文化的に、アメリカは帝国としての役割を終えつつあることを見通している。
『今日地球上にのしかかる全世界的均衡を乱す脅威は唯一つ、保護者から略奪者へ変質したアメリカそのものなのである。己の政治的・軍事的有用性が誰の目にも明らかであることをやめたまさにその時に、アメリカは全世界が生産する財なしにはやって行けなくなっていることに気がつくのである。P265
二十世紀にはいかなる国も、戦争によって、もしくは軍事力の増強のみによって、国力を増大させることに成功していない。フランス、ドイツ、日本、ロシアは、このような企みで甚大な損失を蒙った。アメリカ合衆国は、極めて長い期間にわたって、旧世界の軍事的紛争に巻き込まれることを巧妙に拒んで来たために、二十世紀の勝利者となったのである。この第一のアメリカ、つまり巧みに振舞ったアメリカという模範に従おうではないか。軍国主義を拒み、自国社会内の経済的・社会的諸問題に専念することを受け入れることによって、強くなろうではないか。現在のアメリカが「テロリズムとの闘い」の中で残り少ないエネルギーを使い果たしたいと言うなら、勝手にそうさせておこう。(p279) 』
戦後、半世紀以上にわたって続いたアメリカに対する幻想を捨てるためにも是非、読んでいただきたい本である。2002年の段階で今日のアメリカの状況を予見していたことは特筆に値するだろう。」(引用終わり)
今回は独特のキャラクターでアメリカの要人の懐に入り込み、彼らが日本という国をどう考えているかを聞き出した人の本を紹介させていただく。やはり、彼もアメリカ帝国の終焉を言っている。
著者の伊藤氏は「リアリスト外交」、バランスオブ・パワー(勢力均衡外交)」の視点から、
(1)アメリカの一極覇権外交が失敗してきたこと。
(2)冷戦後の国際構造の多極化が必然的であること。
(3)米経済力の相対的衰退は、マクロ経済学からみて当然であること。
(4)二十一世紀になっても日本の自主防衛政策を阻止しようとする米政府の対日政策は不正で愚かな同盟政策であること。
以上の視点から「日本の独立」の必要性を説いている。自主防衛するのに一番コストパフォーマンスの良いのが自前で核兵器を持つことだとも著者は指摘している。この点についてはいろいろご意見があるだろうが、不思議な言語空間にいる私たち日本人の目を覚ます本であることは間違いない。心に残る一節。
「一九五〇年代中頃、鳩山一郎政権の重光葵外相が、「日本は自主防衛するから、米軍は六年後に日本から撤退して欲しい」とダレスに述べたところ、ダレスは憮然として「お前たち日本人に、そんなことはさせない!」と一蹴したという。日本がまだ非常に貧しかった時、「自主防衛するから、米軍は出ていってほしい」と要求した重光の知性と度胸は、立派なものである。過去半世紀間の日本の政界と官界には、重光のような人物はいなくなった。」(本書57ページ)
評論家の日下公人氏が良い紹介文を書いているので引用させていただく。
固定観念を打破する貴重なアメリカ論
日下 公人
著者の伊藤貫氏は無限大の突進力に加えて情愛の心をもった希有の人である。そういう人には眼前の大事が小事に見える。早く言えば大局観で、それがある人はある人同士の交際をつくることができるが。
長くアメリカに住んだ伊藤貫氏の日米論やアメリカ論にはそれを感ずる。余人の及ばぬ国際関係論が本書にはつぎつぎと開陳されて、本書は日本人の固定観念を打破する貴重な一書になっている。
その骨子はアメリカの一極支配論は間違いで、アメリカはそれを実現できない。したがって世界は多極化し、各国のバランス・オブ・パワー・ポリシー(勢力均衡政策)が交錯する時代になると言うもので、それ自体はごく常識的なものである。
江戸時代の日本人は“強きを挫き、弱きを助ける”のが男のすることで、それがみんなのためになる生き方だと考え、上は徳川幕府から下は町人の一人ひとりまでがそれを実行したが、なぜか戦後の日本外交はちがった。
アメリカは強いと考えて盲従したが、そのおろかさが今年は内外ともにハッキリすると思う。
アメリカは日本を従属させるためには“国際社会から孤立する”との圧力をかければ何でもできると考えたが、今はアメリカの方が孤立しかけていて、時代は刻々と変っている。
それが見える日本人と見えない日本人がいるが、どちらもこの本を読むと良いと思う。ワシントンで活躍する政治家・学者・外交評論家のナマの声がきける。ワシントンにはたくさんの日本人がいるが、外交官でも新聞記者でも学者でも先方とここまでの意見交換をしている人はいない。
無限大への突進力がないサラリーマンばかりだからである。
但し、同じ日本人でもビジネスマンはちがう。商売には双方ともが利益になる解決が必らずあるから、本来、衝突は存在しない。必要なのは無限大への突進力とアイデアで、それは不思議なことだが情愛の念から生まれる。
アメリカには3つの顔があって、第1は、ワシントンのアメリカで、第2は、ニューヨークのアメリカである。どちらも無限大の突進力を自慢にしているので、日本人からみると周囲への情愛と自制心がない。唯我独尊になって、世界に嫌われる。第3は、田舎のアメリカで田舎には自制心と情愛がある。
ところで日本は、ワシントンのアメリカについては多少知っているが、ニューヨークと田舎については、ほとんど知らない。わずかに金融と貿易の人が部分的な体験をもっているだけで、田舎については、現地の工場建設や資源開発で苦労した人が知っているだけである。そういう日本人が書いた日本語のアメリカ論は、不思議なことにアメリカの書店には各種あるが、日本にはない。
また、日本にはアメリカの狡猾さや弱肉強食の略奪主義を指摘する本がない。日本にあるのはアメリカ賛美の本ばかりだから、そういう本を読んで予備知識としている日本のエリートは最初から位負けである。真実に迫る議論をしないから、先方は日本人に会うのは時間の無駄だと思っている。
日本の方も、先方への批判ととられかねない質問はさし控えるのが礼儀だと思っているが、アメリカでは質問できないのは愚鈍か、または相手への愛情不足で距離を置いているからだと解釈される。
その点、ビジネスマンは、商取引実現のためとあらば、何をきいてもいいし、先方も答えてくれる。だから国際交流は、ビジネスマンにさせるのが良いと、かねて思っているが、伊藤貫氏も、なかなかに突っこみ、アメリカは、それに対してまた会おうと答えている。
この本で、読者は伊藤貫氏の人柄とアメリカ人の気質を学なばねばならない。
アメリカが20年前「ユニラテラリズム」を唱えたとき、それは無理だと考えて私は『名誉ある孤立の研究』(PHP研究所刊、1993年)を書いたが、いよいよそうなってきた。
また、10年前にアメリカの略奪主義はいずれ国内の共食いになると書いたが、貧富の差の拡大で中流階級が絶滅危惧種になってきた。
中流がいないアメリカは世界の信用を失っていずれ一極支配はもちろん、勢力均衡戦略もできなくなるだろう。
著者はこの展望をもとに「日本よ、自立せよ」と説いている。(引用終わり)
<参考資料> 少々、古いが、田中 宇氏が世界の多極化について良い解説しているので紹介させていただく。
「資本の論理と帝国の論理」
2008年2月28日 田中 宇
私が自分なりに国際政治を何年か分析してきて思うことは「近代の国際政治の根幹にあるものは、資本の論理と、帝国の論理(もしくは国家の理論)との対立・矛盾・暗闘ではないか」ということだ。キャピタリズムとナショナリズムの相克といってもよい。
帝国・国家の論理、ナショナリズムの側では、最重要のことは、自分の国が発展することである。他の国々との関係は自国を発展させるために利用・搾取するものであり、自国に脅威となる他国は何とかして潰そうする。(国家の中には大国に搾取される一方の小国も多い。「国家の論理」より「帝国の論理」と呼ぶ方がふさわしい)
半面、資本の論理、キャピタリズムの側では、最重要のことは儲け・利潤の最大化である。国内の投資先より外国の投資先の方が儲かるなら、資本を外国に移転して儲けようとする。帝国の論理に基づくなら、脅威として潰すべき他国でも、資本の論理に基づくと、自国より利回り(成長率)が高い好ましい外国投資先だという、論理の対峙・相克が往々にして起きる。
帝国の論理に基づき国家を政治的に動かす支配層と、資本の論理に基づき経済的に動かす大資本家とは、往々にして重なりあう勢力である。帝国と資本の対立というより、支配層内の内部葛藤というべきかもしれない。ただ欧米の場合、大資本家にはユダヤ人が多く、彼らは超国家的なネットワークで動いている。その意味では資本と帝国の相克は、ユダヤとナショナリズムとの相克と見ることもできる。
しかしその一方で、16世紀のスペイン、17世紀のオランダ、18世紀のイギリスと、世界規模の帝国を築いた国々の中枢では、いつもユダヤ人が国際ネットワークの技能を提供しており、それが諸帝国の成功の秘訣の一つだった。欧州のロスチャイルド(ユダヤ)と、アメリカのロックフェラー(非ユダヤ)の対立として描く人もいるが、ロックフェラーは古くから親中国・親ロシアで、多極主義を好む資本家という点でロスチャイルドと同じ側に立っており、両者は根本的な対立をしていない。
産業革命を世界に広げた資本家
資本の論理が大々的に登場したのは、18世紀末にイギリスで始まった産業革命以降である。イギリスでは、産業革命で儲けた人々が産業資本家として台頭したが、しばらくすると彼らは、産業革命が一段落して経済成長が鈍化し始めたイギリスより、まだ産業革命が始まっていないドイツなど外国に投資した方が、儲けが大きいことに気づいた。
投資の利回りが良いのは、産業革命(工業化)が軌道に乗ってから20年間ぐらいで、イギリスでは1780-1800年だった。その後イギリスの成長が鈍化し、資本家が海外へと新規投資先を開拓していった結果、1850-1870年にはドイツで、1880-1900年には日本で、それぞれ産業革命が展開した。
イギリスの資本家が他の国々の産業革命に投資した時、出したものはお金だけではない。イギリスの製造業の技術や、企業経営の技能に加え、封建体制を脱して工業生産に適した社会に転換する過程としての近代化を始めたばかりの日本やドイツなど政府に対し、法律や軍事など近代的国家運営のノウハウまで移植したはずである。その方が新興国家は安定し、資本家の儲けが大きくなる。
ロスチャイルドのような大手の資本家は、イギリスの国家運営に関与し、自分たちの番頭を首相や政治家、高級官僚として送り込んでいたから、イギリスの国家運営の技能を入手するのは簡単だった。ロスチャイルドのようなユダヤ人資本家は、イギリスだけでなくドイツやフランスにも古くからの拠点を持っていた(そもそもロスチャイルドは産業革命前にドイツからイギリスへと拡大した)。だから、資本や産業技術は簡単にイギリスから独仏などに広がり、資本家の儲けを拡大した。
産業革命の進展の結果、1830-70年代に鉄道網が世界中に広がり、同時期に外洋船舶や自動車など交通技術が全般的に大進歩して、世界は1870年代以降「第一次グローバリゼーション」の状況になった。人類史上初めて、世界が単一の市場になる傾向が急速に強まり、資本は成長率の高い地域を求めて投資先を探し、工場は労賃の安い地域を求めて移転し、商品は中産階級が勃興する新興国でよく売れるようになった。資本家は世界的に金儲けでき、資本の論理からすると好ましい展開だった。
資本と帝国の矛盾の末に起きた第一次大戦
しかしそもそも、当時は大英帝国の政治覇権が世界を安定させていたパックス・ブリタニカの時代だった。イギリスが帝国の論理に基づいて世界を安定的に支配していたからこそ、資本家は世界的に儲けられた。
世界には、工業技術の修得がうまい人々と、そうでもない人々がいる。日本やドイツなどの人々は、イギリス人よりも安く優れた工業製品を作れるようになった。欧州各国から移民を集めて作られたアメリカも、イギリスより良い工業製品を作り出した。イギリスは、最初に産業革命を起こし、パックス・ブリタニカで世界を安定させている功労者であるにもかかわらず、産業的には独米日などより劣る、儲からない国になる傾向がしだいに顕著になった。19世紀末には、資本の論理と帝国の論理の間の矛盾・対立が拡大した。
矛盾が拡大した果てに起きたのが、1914年からの第一次世界大戦だった。前回の記事にも書いたように、イギリスは外交・諜報能力が非常に進んでいたが、軍事製造力でドイツに抜かれるのは時間の問題だった。イギリスは、ドイツが東欧・バルカン半島からトルコ・中東方面に覇権を拡大するのを阻止する目的もあり、フランスやロシアを誘ってドイツとの戦争を起こした。
ドイツにも投資していたイギリスの国際資本家の中には、イギリスが戦争でドイツを潰そうとしていることに、ひそかに反発した人々もいたふしがある。彼らは、英政府に軍事費を無駄遣いさせたり、欧州のユダヤ系革命勢力がロシアに行くよう誘導して革命を起こし、イギリスと組んでドイツと敵対していたロシアが革命で戦線離脱するよう仕向けたりして、第一次大戦でイギリスが消耗し、帝国として機能できない状態に陥れようとした。こうした暗闘の結果、第一次大戦は長引き、イギリスは最終的に勝ったものの、国力を大幅に落とした。
第一次大戦でイギリスが勝てたのは、アメリカを参戦させることに成功したからである。当時すでにニューヨークには資本家が数多くおり、第一次大戦でイギリスではなくドイツを支援する勢力も多かったが、イギリスの強い勧誘活動の結果、アメリカはイギリス側に立って参戦した。その見返りとして米政府は、戦後の世界体制を多極的なものにするための主導権を得た。
アメリカを乗っ取ったイギリス
アメリカが主導して構築した第一次大戦後の世界体制が、国際連盟であり、ベルサイユ体制だった。これは、大国どうしで話し合って世界の安定を維持する戦争防止の国際機構になるはずのもので、イギリスがドイツを潰すような戦争の再発を防ぐ資本の論理と、アメリカは南北米州のことだけに責任を持ち欧州の紛争に巻き込まれないという不干渉主義の両方が満たされるはずだった。しかし、アメリカ自身が議会の反対で参加せず、機構は不完全なものに終わった。
その後、イギリスは20年かけてアメリカの連邦政府を覇権的な機関に作り替え、アメリカが地方分権の不干渉主義から連邦政府独裁の覇権国へと転換するよう誘導した。その上で第二次大戦を起こして米英が勝ち、第一次大戦で終わっていたイギリス覇権を、アメリカ覇権(パックス・アメリカナ)として再生した。
アメリカの連邦政府は権限が拡大し、戦争をしやすい機関に作り替えられ、アメリカが「戦争中毒」になる素地が作られたが、その裏にはアメリカを作り替えて世界支配をやらせようとしたイギリスがいた。最初の戦略はイギリスが立案したが、その後はアメリカにCFR(外交問題評議会)などイギリスからコピーされた研究機関が作られ、英諜報機関のMI6が米に移植されてCIAとなり、アメリカ自身がイギリス好みの世界戦略を考案するようになって、イギリスがアメリカに乗り移る過程が完了した。
私はこれまで「アメリカはイギリスから覇権を移譲された」と書いてきたが、よく考えると「イギリスは自国の衰退を補うため、アメリカを取り込んで米英同盟が覇権を握る体制にした」と言った方が良い。
アメリカは第二次大戦でも世界の多極的体制を希求し、国際連盟に替えて国際連合を作ったが、新体制はイギリスの冷戦の策略を受け、1950年の朝鮮戦争までに無力化された。おそらくイギリスは、第二次大戦中から、戦争中は日独を潰すためにソ連を味方につけるが、その後はソ連を敵にして米英が中ソと対立する体制を作るつもりだったのだろう。
アメリカの覇権のもとで世界が安定したら、再び資本家はグローバリゼーションを起こし、儲けるために中ソに投資して成長させ、不干渉主義のアメリカはそれを容認し、イギリスの覇権は10年で崩れただろう。戦後すぐに冷戦構造を作って世界を分断し、先進国をすべて英米覇権下に置いたことで、イギリス黒幕の米英同盟による覇権は長期化し、現在まで続いている。
(実際、1990年代に冷戦が終わった直後から第2次グローバリゼーションが始まり、それから10数年後の今、中国は経済大国として台頭し、ロシアも資源大国になり、世界は多極化している)
ニクソン以後に暗闘再燃
イギリスが、アメリカを引っ張り込み、日独を潰して傘下に入れ、中ソを永久の敵にして、米英同盟が世界を支配する体制を1950年に完成させた時点で、1910年代からの資本と帝国の暗闘・葛藤は、いったんは帝国の勝利で確定した。
イギリスが召集してアメリカで開いた1944年のブレトンウッズ会議で、ドルは基軸通貨となり、アメリカは造幣輪転機を回すだけで富を生み出せるようになった(建前は金本位制だったが、米政府はかまわずドルを増発した)。西欧や日本に対する戦後復興投資も米企業の儲けとなり、資本家は1960年代までの20年間は、儲かるので米英中心の世界体制に文句を言わなかった。
ところが60年代に米経済の成長や欧日の復興が一段落した後、資本家は再び満足しなくなり、70年代にかけて政府にドルを全力で増発させ、71年に金ドル交換停止を引き起こし、ブレトンウッズ体制を潰すという覇権の自滅をやり出した。同時期にニクソン訪中があり、その後は米ソ雪解け、レーガンによる冷戦終結まで、アメリカは20年かけて断続的に冷戦体制を壊していった。
多極主義に基づいてアメリカの自滅を画策したニクソンは1974年のウォーターゲート事件で辞めさせられた。この事件の騒動からは、アメリカのマスコミを操っているのはイギリスの側であり、資本家の側ではないことが感じられる。ニクソンを辞任に追い込んだ米マスコミは「悪を退治した正義の味方」として描かれ、その後、世界中の多くの若者が英雄談にひかれ、ジャーナリスト志望になった(かつての私自身も)。だが、これは実はイギリス系の謀略であり、ヒットラーや東条やサダムフセインを極悪に描いたのと同じ、イギリスお得意のマスコミを使った善悪操作の戦略だった。
ニクソン以後、アメリカ側が冷戦終結に向けて動いたのに対抗し、イギリスは、イスラエルをけしかけて米政界に食い込ませた。イスラエルはもともと、イギリスの中東支配の道具として、アラブにかみついて分断・従属させる番犬(羊の群に対するシェパード犬)として建国を容認された国だった。だが、イギリスが国力低下の末に1967年、中東(スエズ以東)からの撤退を決めたため、梯子を外されてイスラエルは危機に陥った。(選民思想のユダヤ人は、羊の群れを飼い主の代わりに一定方向に進ませる牧羊犬シェパードのように、遅れた他の民族を誘導する、神様のためのシェパードを自称している。だが現実のイスラエルは、神様ではなくイギリスの番犬だった)
危機を乗り越えるため、イスラエルはまず67年に第3次中東戦争を起こしてパレスチナからアラブ諸国(エジプト、ヨルダン、シリア)を追い出してガザ、西岸、ゴラン高原を占領した。同時に米政界に食い込み、アメリカの中東戦略をイスラエル好みのものに変えることで国家存続をはかる戦略を開始した。イスラエルは、イギリスの有能なシェパードとしてアメリカに食いつき、抵抗勢力に「ユダヤ人差別」のレッテルを貼って噛みついた。
イスラエルとの暗闘
イスラエルはイギリスから、議員への圧力のかけ方、軍事産業との結託の仕方、マスコミの操作術など、アメリカを牛耳るノウハウを提供され、数年で米政界に食い込み、1980年に当選したレーガン政権に政策立案者としてイスラエル系の勢力(のちのネオコン)が数多く入り込んだ。
アメリカの世界戦略をめぐる資本家とイギリスの暗闘は、資本家とイスラエルの暗闘に変質した。以前の記事に書いたように、もともとイスラエルの建国をめぐっては、ロスチャイルドなど資本家ユダヤ勢力と、活動家ユダヤ勢力(シオニスト)との間に暗闘があったが、その暗闘は数十年後にアメリカで再発した。
資本家の側は、必要以上に過激なシオニスト右派勢力をアメリカで構成して1970年代後半以降イスラエルの入植地に送り込み、イスラム側とのいかなる和平も許さない過度な強硬姿勢をイスラエルに植え付け、イスラエルが好戦的にやりすぎて自滅していく方向に誘導した。
イスラエルの代理をつとめるふりをして実は資本家の代理というスパイ的な勢力は、イスラエル側の入植者(リクード右派)だけでなく、米側のネオコンも同様だった。ネオコンが入り込んだレーガン政権は、ソ連のゴルバチョフと談合して冷戦を終わらせ、ドイツを統合するという、イギリスの世界戦略を潰す大事業を挙行した。
また、レーガンは2期目の最後の1988年、アラファトを亡命先のチュニジアからパレスチナに呼び戻し、パレスチナ国家の建設に道を開いた(任期最後の年にやることでイスラエルの妨害を避けた)。1993年のオスロ合意につながるこの動きは表向き、パレスチナ問題を解決してイスラエルの安定に貢献する戦略とされたが、実際には、パレスチナ国家の創設後、ゲリラが出てきて以前より有利な位置からイスラエルを砲撃する可能性があった。
イスラエルはアメリカに引っかけられて潰される懸念があると気づき、いったんオスロ合意で結んだ和平を、その後破棄した。和平を破棄したことで、イスラエルでは右派(入植者)の政治力が強まったが、右派もイスラエルを潰そうとする米資本家が送り込んだスパイだったことは、すでに述べたとおりだ。
テロ戦争で巻き返そうとした英イスラエル
冷戦終結は資本家の勝利だったが、その後、イギリスが反乱してこないよう、冷戦終結と並行して起きた第2次グローバリゼーションで、アメリカだけでなくイギリスも大儲けできる金融システムが採用され、ロンドンはニューヨークと並ぶ世界金融の中心となった。だが1997年のアジア発の国際通貨危機は、米英中心の金融覇権が永続しないことを感じさせた。
(通貨危機の際、IMFが東南アジアや中南米諸国に過度に厳しい借金取り戦略を採り、反米感情を煽った行為には、隠れ多極主義の臭いがする)
その後イギリスは、イスラム側と戦うイスラエルや、軍事予算増を求める米の軍産複合体ともに「第2冷戦」的なイスラム過激派との永続的テロ戦争を画策した。アメリカでは99年ごろから「近いうちにイスラム教徒によるテロがある」と喧伝され、01年の911でそれが現実化した。この前後、マスコミを使ってイスラム側を極悪に描く、イギリスお得意の善悪操作術が展開された。
マスコミ制御を英イスラエル側に取られ、議会では反イスラエルの言動も許されないがんじがらめの状況下で、現ブッシュ政権が採った戦略は「英イスラエルの意のままに動きつつ、それを過激にやりすぎることで、英イスラエルの戦略を潰す」という、隠れ多極主義だった(レーガンやニクソンも似た戦略を採っており、ブッシュ政権の発明ではないが)。
ブッシュ政権の隠れ多極主義は今、成功の直前まできている。ブッシュは今年、任期末なので再選努力をする必要もなく、イスラエルに気兼ねせず好き放題ができる。イスラエルは、イスラム側との自滅的な最終戦争にいつ突入してもおかしくない。イスラエル軍が予定しているガザ大侵攻が、大戦争の幕を落としそうだ。
金融界では、連銀のグリーンスパン前議長が先日、アラブ産油国(GCC)にドルペッグ破棄を勧めた。連銀のバーナンキ現議長は「アメリカの不況はひどくなる」と景気に冷水を浴びせる発言を何度も繰り返している。いずれも、金融とドルの覇権の大舞台を支える大黒柱を斧で切り倒そうとする、多極化誘発の言動である。かつてイギリス好みの戦争機関の一部だった米連銀は、今では隠れ多極主義の資本家の手先に成り変わっている。
イギリスをEUに幽閉する
アメリカが金融崩壊していくと、同じ金融システムに乗っているイギリスも連鎖的に崩壊する。以前の記事に書いたように、イギリスは今年、金融財政の危機になると予測されている。スコットランドでは、イギリスから分離独立を目指す動きも続いており、独立支持の元俳優ショーン・コネリーは最近、77歳の自分が死ぬ前にスコットランドは独立すると発言している。
米英同盟の崩壊、金融財政危機と国土縮小の末、イギリスはアメリカを操作して世界を間接支配することができなくなり、EUに本格加盟せざるを得なくなるだろうが、EUでは今、リスボン条約などによって、政治統合が着々と進んでいる。独仏はすでに軍事外交の統合で合意しており、イギリスもEUに本格加盟するなら、軍事外交の権限をEU本部に明け渡さねばならない。
これは、イギリスが外交力を駆使してアメリカを牛耳ることを永久に不可能にする。アメリカの資本家から見れば、いまいましいイギリスをEUに永久に幽閉することができる。
イギリスは、EUを牛耳って覇権の謀略を続けようとするかもしれないが、かつて二度もイギリスに引っかけられて潰された上、50年の東西分割の刑に処されたドイツは、もう騙されないだろう。サルコジのフランスも、親英的なふりをしつつ実際には多極化の方に乗る狡猾な戦略を展開している。独仏とも、イギリスの長年の謀略から解放されたいはずである。
アメリカは、イギリスとイスラエルから解放されて国際不干渉主義に戻っていくだろうし、ロシアや中国や中東(GCC+イラン+トルコ)も、米英覇権から抜け、独自の地域覇権の勢力になっていくだろうから、たとえイギリスがEUを牛耳れたとしても大したことはできず、世界は多極化していくだろう。アメリカを好戦的にしていたイギリスとイスラエルが無力化されることで、世界は今より安定した状態になることが期待できる。






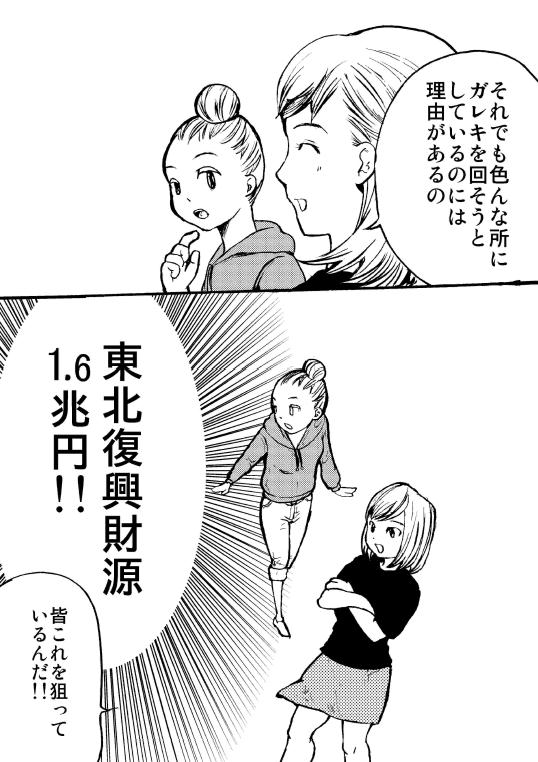

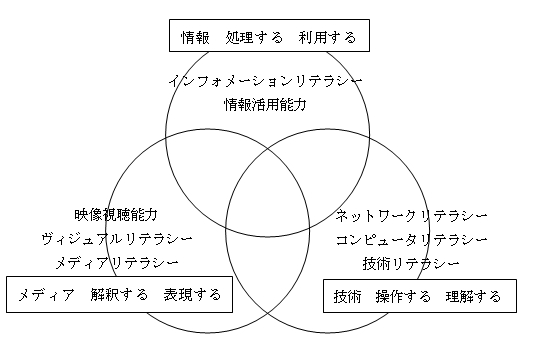
 Follow me on Twitter
Follow me on Twitter