一部日本のマスコミが囃し立てている「シェルガス革命」について、大変、興味深い指摘があるので、紹介する。以前、高貴なる嘘という概念を紹介したが、(「高貴な嘘」(ノーブル・ライ)という概念はプラトンの「法律」という本に書かれていたものだ。悪意で解釈すれば、「嘘も100回言えば真実だ」(ゲッペルス)ということだ。善意で解釈すれば「子供には神話を最初に教える必要がある。ある程度物が分かるようになってから科学を教えても遅くはない。それが教育的な配慮だ。」と言うものである。大衆を騙すのは権力者にとって必要悪?であるという考え方である。)現在、米国勢が囃し立ているシェルガス革命についても、過去の原子力平和地用や、二酸化炭素による地球温暖化のように、いろいろ思惑があるようである。
今回は、ル・モンド記事と元外交官原田武夫氏の興味深い指摘をご紹介する。(以下)
~エネルギー事情の大転換となるか、景気の一時的活性化に終わるか?~
「大いなるペテン、シェールガス」
ナフィーズ・モサデク・アーメド
(政治学者)ブライトン開発政策研究所(イギリス)所長
(訳:鈴木久美子)
安価なエネルギーと引き換えに長期にわたる汚染を引き受けねばならないのだろうか。シェールガス・シェールオイルの採掘に関わるジレンマにアメリカの企業も政府も悩んでいない。10年もたたないうちにこの新しい資源はアメリカの経済成長を軌道に乗せ、雇用を活性化し、国際競争力を復活させるだろうというのだ。しかしこの《エネルギー革命》がすぐつぶれるバブルに過ぎないとしたらどうか? [フランス語版編集部]
« 原文 »
アメリカメディアによるとシェールガス・シェールオイル「革命」による経済の飛躍的発展が予測され、アメリカは間もなく「黒い金(きん)」の恩恵に浸ることになるという。国際エネルギー機関(IEA)の『世界エネルギー展望2012年版』によれば、2017年度にはアメリカはサウジアラビアから世界第1位の産油国の座を奪って、エネルギーに関して「ほぼ自給自足」となる。IEAによると炭化水素の計画的な生産上昇は、2011年の一日当たりの8400万バレル[原油1バレルは約159リットル――訳注]から2035年には9700万バレルになるだろうとされ、それは「すべて液化天然ガスと非在来型エネルギー資源(主にシェールガスとシェールオイル)から」生じるとされている。一方で在来型エネルギー資源の生産量は2013年から下降するであろう。
シェールガスは水圧破砕(水と砂と洗剤の混合物に圧力をかけ注入して頁岩にひび割れを作り、そこからガスを取り出す)と、水平掘り(これにより必要な地層をより長時間にわたって叩くことが可能になる)によって採掘されるが、広範にわたる環境汚染を代償にして得られるものである。しかしアメリカでの採掘は数十万人の雇用創出へとつながり、豊富で安価なエネルギーという利点を与えてくれる。2013年の『エネルギー予想――2040年に向けて』(エクソンモービル・グループ)のレポートによれば、世界のガス需要の急速な伸びという状況にあっても、アメリカはシェールガスのおかげで、2025年から明らかに炭化水素の輸出国となるという。
そして「シェールガス革命」が回復期にある世界経済を強くするばかりでなく、投資バブルをはじけんばかりにふくらませるとしたらどうだろう? 経済は病み上がり状態だし、近年の経験から言っても、このような浮かれ騒ぎに対して慎重な態度を促さなくてはならないはずなのだが。スペイン経済を例にとると、かつては隆盛を誇っていたのが(2008年にはEU圏で第4位の勢力)、盲目的にしがみついていた不動産バブルが突然崩壊して以来、ひどい状態になっている。政治家たちはこの2008年の危機からほとんど教訓を引き出してはいない。彼らは同じ過ちを化石燃料で繰り返す危険があるのだ。
ニューヨーク・タイムズの2011年6月の調査報告はシェールガス「ブーム」のなかでメディアと石油・ガス業界の間に早くも生じた亀裂を暴露している。その号では専門家たち(地質学者、弁護士、市場アナリスト)が抱いた疑惑を公にしているのである。
石油会社の発表は、「故意に、不法なまでに採掘生産量と埋蔵量を多く見積もっている(注1)」という疑惑が表明されている。同紙の説明によれば、「地下の頁岩からのガスの抽出は石油会社がそうみせかけているよりももっと難しく、もっとコストがかかるはずで、その証拠として、この問題について業者間で交わされた数百の電子メール、資料ばかりでなく、数千の採掘抗について集められたデータの分析報告がある」。
2012年の初頭に、アメリカの2人のコンサルタントがイギリスの石油業界の主要誌『Petroleum Review』で警鐘を鳴らしている。二人は「アメリカのシェールガスの鉱床の信頼性と持続性」について検討を加え、業者たちの予測がアメリカ証券取引委員会(SEC)の新しい規則に沿って行われたものであることを強調している。SECは投資市場の監視をする連邦委員会である。この規則は2009年に採択されたもので、石油会社に備蓄量を好きなように計上することを許可しており、独立機関による調査は行われないのである(注2)。
業者たちは頁岩のガス鉱床を過大に見積もることによって、採掘に伴うリスクを二義的な問題にしてしまうことができる。ところが水圧破砕は環境に有害な影響を及ぼすだけではない。まさに経済的な問題をも引き起こす。水圧粉砕は非常に寿命の短い生産しかおこなわないからだ。雑誌『ネイチャー』で、英国政府の元科学問題顧問のデヴィッド・キング氏はシェールガス井の生産性は最初の1年の採掘で60~90%低下すると力説する(注3)。
これほど急激な生産性低下では明らかにわずかな収益しかもたらされないことになる。ガス井が涸れてしまうと作業員たちは大急ぎで他のところへ採掘に行って生産量のレベルを維持し、資金返済に充当しなくてはならない。条件が整えば、このような自転車操業で数年間は人の目を欺くことができる。このようにして、シェールガス井採掘は脆い経済活動と結びつき(持続力はないが、短期間には瞬発力を発揮して)、アメリカで急激な天然ガスの価格低下を引き起こした。2008年には100万BTU(イギリス熱量単位)7、8ドルだったものが2012年には3ドルを割った。
投資の専門家たちは騙されない。「水圧粉砕は景気を粉砕する」とジャーナリストのウルフ・リヒターは『ビジネス・インサイダー』で警告している(注4)。「採掘は猛スピードで資本を食いつくし、生産が行き詰ると業者に借金の山の上を残してきた。この生産量の低下で経営者たちの懐を痛めないようにするために、企業は次から次へと汲み上げなくてはならなくなり、涸れた油井の分を他の油井で補うのである。他の油井も明日には涸れるだろう。悲しいかな、遅かれ早かれこういう図式は壁に突き当たる。現実という壁である」。
ブリティッシュ・ペトロリアム(BP)との合併前の石油会社アモコ(Amoco)で働いていた地質学者のアーサー・バーマンは「信じられない速さ」で鉱床が涸れていくことに驚きを示している。バーマン氏はテキサスのイーグル・フォード鉱区(最初のシェール油田)を例に挙げて、そこでは「年間採掘量が42%以上低下した」と言う。安定した生産量を保つためには業者は「毎年追加で約1000の油井を同じ鉱区で掘らなくてはならない。それは、1年に100億から120億ドルの支出となる。全部合計すると2008年の金融業界への資金投入額の合計に達する。企業はどこでこの資金を調達できるというのだろう?(注5)」。
ガスバブルの最初の影響はすでに世界大手石油企業に及んでいる。2012年の6月にエクソンモービルの代表取締役のレックス・ティラーソン氏が窮状を訴えた。アメリカの在来型天然ガス価格の下落は消費者にとっては確かに幸運だったが、売り上げの激減の痛手を受けたエクソンモービルには致命傷となったと述べた。そして株主を前にエクソンモービルはガスによる損失はないと偽ったものの、ティラーソン氏はアメリカでもっとも影響力のあるシンクタンクの一つである外交問題評議会(CFR)でお涙頂戴型の演説をして「わが社は資産が尽きようとしている。もう収入は得られない。経営は赤字だ(注6)」と述べている。
ほぼ同時期に、イギリスのガス会社であるBGグループが「アメリカの天然ガス事業部門で資産が13億ドルに低下したこと」すなわち「中間決算で明らかな減益」の窮地に立たされていることを認めた(注7)。2012年11月1日、ロイヤル・ダッチ・シェルの四半期の決算報告が3期連続で不振で年間累積24%の低下となったのを受け、ダウ・ジョーンズの広報担当はこの悪いニュースを伝えるに当たって、証券業界全体におけるシェールガスブームによって引き起こされるであろう「損害」について警告した。
万能薬からパニックへ
シェールガス競争の中のパイオニアであるチェサピーク・エナジー社もバブルは免れなかった。負債の重みに押しつぶされたチェサピーク・エナジーは債権者の手形決済のために資産の一部売却(ガス田とパイプラインの合計69億ドル)を余儀なくされた。「チェサピーク・エナジーは社長のおかげでシェールガス革命のリーダーになったのに、活動領域を少々減らすようになった」とワシントン・ポストは遺憾の意を表した(注8)。
どうしてこの「革命」のヒーローたちはこれほどまでに落ちたのだろうか? 経済評論家ジョン・ディザードは2012年5月6日付『フィナンシャル・タイムズ』でシェールガス企業が「自己資本を2倍、3倍、4倍さらに5倍も上回る額を使い果たして土地を購入し、井戸を掘り自分たちの計画を実現しようとした」と指摘している。ゴールドラッシュの資金繰りのためには、膨大な金額を「複雑で面倒な条件で」借りなければならない。しかし、ウォール街は通常の行動規則を曲げてくれるようなことはしない、ディザードによればガスバブルはそれでもふくらみ続けているという。その理由は経済的な危険性をはらんだこの資源にアメリカが依存しているからである。「シェールガス井の生産性の持続しない一時的性格を考慮して、掘削は続けられなければならない。シェールガス価格は高くなり、高騰すらして落ち着くだろう。過去の負債だけでなく現在の生産にかかる費用に充当するためである」。
それでもなおいくつもの大手石油会社が同時に経営崩壊に直面するということはありうる。もしこの仮説が立証されるなら「2、3社の倒産か大掛かりな債務処理にまきこまれてしまい、債務処理の名目で各企業はシェールガス事業を撤退し資本が消えてしまうだろう。これは最悪のシナリオだ」とバーマン氏は語る。
言い換えれば、シェールガスはアメリカ、あるいは全人類を「ピークオイル」(「ピークオイル」とは、地理的制約と経済的制約から原油の採掘が困難で巨額を要するとされるレベル)から守るという議論はおとぎ話にすぎないことになる。最近公表された独立性の高い科学レポートによれば、シェールガス「革命」はピークオイルに猶予を与えてくれないと確証している。
雑誌『Energy Policy』に発表された研究によると、キング氏のグループは、石油産業は化石燃料の世界埋蔵量を3分の1多く見積もったという結論に達した。まだ採掘可能な石油鉱床は8500億バレルに満たないのに、公式な見積もりではおよそ1兆3000億バレルと言われている。『Enegy Polocy』の寄稿者たちによると、「化石燃料資源が地球の深いところに確かに大量に存在しているが、世界経済が通常持ちこたえられるコストで採掘できる石油の量は限られており、短期間のうちに衰退の一途を辿るはずだ(注9)」という。
水圧破砕によって得られた宝、シェールガス・シェールオイルがあるにもかかわらず、現実の埋蔵量は年間推定で4.5ないし6.7%のペースで減少している。そのためキング氏らの研究チームはシェールガスの採掘がエネルギー危機を救うという見解を断固として拒否している。キング氏と同じ立場で、経済評論家のゲイル・トヴェルバーグ氏は在来型化石燃料の世界生産量が2005年をピークに伸び悩んでいることをあげている。彼は2008年と2009年のリーマンショックの主な原因のひとつはこの停滞にあると見て、これが現在の景気後退をさらに深刻化させる可能性を予告しているという(シェールガスがあろうが、あるまいがこれは起こるという)(注10)。それだけではない、新経済基金(NEW)はIEAの報告書に続いて出した新しい研究で、オイルピークの出現を2014年ないし2015年と予測しており、そのとき採掘と供給にかかる費用が「世界経済がその活動に致命的なダメージを受けることなく引き受けることのできる費用を追い越すだろう」(注11)とみている。
この研究はメディアの関心を引かなかったし、エネルギー業界のロビイストの宣伝文句に浸りきっている政治家たちの関心も引かなかった。遺憾なことである。この研究の結論はわかりやすいからだ。景気を修復するどころか、シェールガスは作り物のバブルをふくらませ、根本的に不安定な構造を一時的にカムフラージュしているのである。バブルがはじけると供給の危機と価格高騰をおこし、世界経済に甚大な悪影響を及ぼす危険性があるのだ。
——————————————————————————–
<注>
(1)«Insiders sound an alarm amid a natural gas rush», The New York Times, 25 juin 2011.
(2)Ruud Weijermars et Crispian McCredie, «Inflating US shale gas reserves», Petroleum Review, Londres, janvier 2012.
(3)James Murray et David King, «Climate policy : Oil’s tipping point has passed», Nature, no 481, Londres, 26 janvier 2012.
(4)Wolf Richter, «Dirt cheap natural gas is tearing up the very industry that’s producing it», Business Insider, Portland, 5 juin 2012.
(5)«Shale gas will be the next bubble to pop. An interview with Arthur Berman», Oilprice, 12 novembre 2012, http://oilprice.com
(6)«Exxon : “Losing our shirts” on natural gas», The Wall Street Journal, New York, 27 juin 2012.
(7) «US shale gas glut cuts BG Group profits », Financial Times, Londres, 26 juillet 2012.
(8)«Debt-plagued chesapeake energy to sell $6,9 billion worth of its holdings», The Washington Post, 13 septembre 2012.
(9)Nick A. Owen, Oliver R. Inderwildi et David A. King, «The status of conventional world oil reserves – Hype or cause for concern ?», Energy Policy, vol. 38, no 8, Guildford, août 2010.
(10)Gail E. Tverberg, «Oil supply limits and the continuing financial crisis», Energy, vol. 37, no 1, Stamford, janvier 2012.
(11)«The economics of oil dependence : A glass ceiling to recovery», New Economics Foundation, Londres, 2012.
(ル・モンド・ディプロマティーク日本語・電子版2013年3月号)
2013年 4月4日
「シェール革命という高貴なウソを信じる日本」
~インテリジェンスのプロ、原田武夫氏が大胆分析~
先日、杜の都・仙台に出張したときの話だ。繁華街・国分町の片隅で設けた会食に出席された地元財界幹部の一人の方が、上気した面持ちで私に向かってこう語りかけてきた。「原田さん、『シェール革命』ってやつはすごいね。何せこれからアメリカでは無尽蔵に採掘できて、しかも温暖化効果ガスの排出量が圧倒的に少ないっていうのだから、エネルギーの未来は、もうこれで決まりなのではないですか」
シェール革命に納得できず
同席していたわが国アカデミズムの重鎮の一人も、続いて口を開いた。「確かにそうですね。仮にアメリカがシェール革命を推し進めるとなると、今、東北大学を中心に取り組んでいる地域経済活性化のための次世代移動体研究プロジェクトがこのままでは失速してしまう危険性があるのです。なぜならばその柱のひとつである電気自動車(EV)は、現状では原子力発電が安定的に継続することを前提としていますから」
私からすれば、いずれも人生の大先輩である。普段ならば黙ってうなずくだけで、特に何も申し上げなかったはずだ。しかしこのときだけは違った。どうにもこうにも納得するわけにはいかなかったからである。「申し訳ありませんが、『シェール革命』は本当に起きるのでしょうか。私は正直言ってかなり懐疑的です」。居住まいを正して私はそう切り返した。
私の著書最新刊『「日本バブル」の正体~なぜ世界のマネーは日本に向かうのか』(4月4日刊行)でも詳しく書き、かつその新刊記念講演会(リンクはこちら)でもじっくりお話しすることなのであるが、「シェール革命」と聞くとどうしても納得がいかないことがいくつかあるのだ。思いつくままに書くならば次のとおりとなる。
◎鳴り物入りで始まった「シェール革命」だが、特にシェールガスはパイプラインがなければアメリカは輸出することができない。その肝心のパイプラインがまったく整っていないのが現状である以上、シェールガスがアメリカから世界、とりわけわが国に向かって噴き出してくるのは“今”ではなく、“将来”である。今から大騒ぎすべき話ではない。
◎つまり「シェール革命」が最盛期を迎えるまでにはまだ時間があるのだが、その間、ほかの国々が指をくわえて待っているとは考えづらい。ナイジェリアなどほかの産出国は温暖化効果ガスこそ大量に出るものの、従来型の天然ガスや原油のダンピング(廉売)を一斉に始めるはずだ。そうなった場合、採掘に費用がかかるため高めの価格設定しかできないシェールガス/シェールオイルにまで触手が伸ばされるのかは甚だ疑問である。
◎ さらには「シェール革命」と言いつつ、アメリカ自身が次世代移動体として電気自動車や水素燃料電池車の開発を加速させているのが大いに気になる。実際、オバマ政権はこの方向に具体的な形で歩み出しており、3月15日にイリノイ州で行った演説で同大統領はこれら「ガソリンを使わない自動車」の実用化のため、今後10年間で20億ドルほどを拠出すると表明したばかりなのである。「シェール革命一本であくまでも行く」という気合いは微塵も感じられないのだ。
「高貴な嘘(noble lie)」という言葉がある。「リーダーたるもの、全体利益の実現のためには時にウソをつかなくてはならないこともある」といった意味合いだ。アメリカはこれまで何度となく「高貴な嘘」でわが国、そして国際社会を翻弄してきた。2003年に行われたイラクに対する武力行使の際、「イラクで大量破壊兵器を見つけた」と国連安保理の場で生真面目な軍人・パウエル国務長官(当時)を使って一大プレゼンテーションを行わせたのがその典型例だろう(その内容はその後、同国務長官自身が吐露したように「真っ赤なウソ」であったことが明らかとなる)。
よもや「あのアメリカがここまで正々堂々とウソをつくとは」と思うかもしれないが、それが国際場裏における現実なのだ。そして現状を見るかぎり、誰でも気づくことのできる上記のような「疑問」を踏まえれば、私には「シェール革命」が手の込んだ「高貴な嘘」に思えて仕方がないのである。
アメリカの深謀遠慮とは?
「なぜそこまで手の込んだことをアメリカはするのか。シェール革命でいちばん儲けられるのは自分なのであるから、ウソなどつく必要ないのではないか」。読者からそんな反論が聞こえてきそうだ。しかし大変失礼ながら、そう思われた読者の方は人気漫画「北斗の拳」ではないが、“お前はもう死んでいる”のである。なぜならばまさにここにこそ、アメリカの深謀遠慮が潜んでいるからである。考えられるシナリオはいくつかある。
まずいちばん単純に「シェール革命」が本当に推し進められる場合を想定しよう。実のところシェールガス/シェールオイルの鉱床は確認されているだけでもアメリカ以外の世界各地に存在している。中国や中南米などであるが、問題は現状の天然ガスや原油の価格では採算がとれない点にある。したがってこのシナリオにおいて関係各国はいずれも、石油・天然ガスが最も産出されている中東地域が「有事」となり、そこでの生産が不可能となることを強く期待することになる。イスラエルによる対シリア攻撃をきっかけとしたイランとの本格的な戦闘開始、そして「中東大戦争」への発展がその先には見えてくる。
現状では今年秋にもありうる展開であるが、そうなった場合、世界中の株式マーケットは全面安だ。マネーは逃げ場所を求めて日本円に殺到、強烈な「円高」となるわけである。オイルショックに見舞われた世界は、アメリカに「シェール革命」の推進を要請するはずだ。一方、サウジアラビアやイスラエルは戦乱で勝ち残るため、アメリカ製兵器を続々と購入し続けるに違いない。アメリカにとっては一挙両得というわけなのである。
だがここで困るのが中東地域以外の産油国、特にロシアである。通常の天然ガスや石油をめぐる最大のプレーヤーであるロシアは「シェール革命」に反対すべく、中東開戦を阻止し続けようとする可能性が高い。その結果、このシナリオは頓挫してしまう危険性をはらむ。
問題はアメリカにとっても、「そんなことは先刻お見通し」であるはずだという点なのだ。つまりこのとき、アメリカの真意は「シェール」にはない。そしてそうであるとき、アメリカは実のところ周囲をアッと驚かせる次世代エネルギー技術をすでに開発しているはずでもあるのだ。しかしそれをあえて出さずに「シェール革命」なる用語を“捏造”し、しかも天然ガスを今や世界中で買い漁っているわが国にこうささやきかけているのである。
「パイプライン設置のために投資をしてくれたらば、最優先でシェールガス/シェールオイルを特別に分けてあげてもいい。福島第一原発事故の余波で貴国は大変でしょう」
これに“日米同盟”という美辞麗句がつけられれば、わが国要人たちがこれに抗することはまずない。進んで資金提供し、巨大プロジェクトの完成を今や遅しと待つことになるはずだ。むろん、アメリカも日本側協力者に鼻薬をかがせることを忘れないはずだ。たとえば時代はさかのぼって第2次世界大戦後の1950年代、アメリカ国防総省の支援により設立された「日本開発会社」は、いくつかの復興のための巨大インフラプロジェクトに関与していたことが史料から明らかになっている。
しかしそのための資金としてアメリカ国防総省から捻出された資金は、戦後最大の政治プロデューサー「児玉誉士夫」を経由して、わが国政財界の闇へと消えて行ったのである(有馬哲夫『児玉誉士夫 巨魁の昭和史』(文春新書)参照)。「インフラ開発に日本を絡ませたときには駄賃がいる」。そうアメリカ側は伝統的に認識しているはずなのであって、わが国からパイプライン建設にマネーが流れれば流れるほど、その一部がわが国へと還流され、再びわが国政財界の闇に消えることは大いにありうる、と歴史家ならば断言するはずだ。むろん、私や読者の皆さんのような庶民の知らないところで。
それでは私たち日本人は、ただひたすら手をこまぬいて見ていなければならないのか。またそもそもアメリカはこの場合、いわば「捨て駒」となるシェール革命ではなく、実際のところ何を追求しているというのであろうか。
次世代の「本命」はシェールではなく、水素
簡単に書くならば、まず前者についてひとつの「光」を先日、わが国の神奈川県・寒川にあるとあるヴェンチャー企業Q社で私は目の当たりにした。シェールガスといっても炭酸ガスは出てくる。ところがこの企業が開発した技術ではこれを「炭酸化ナトリウム」と「水素ガス」へと分離できるのである。つまり「排ガスから燃料ができる」わけで、驚愕の技術なのだ。アメリカがシェール革命を推し進めれば進めるほど、その後ろについてこれを売ることで、わが国は巨利を得ることができる代物なのである。こうした革新的な技術を私たちは大切に育て、全面開花させなければならない。
一方、後者について言うならば、アメリカにとっては実のところ宿敵であるイギリスの態度を見れば答えはすぐ出てくる。上記の拙著でも書いたことだが、イギリスは2015年までに水素エネルギーによる燃料電池車の完全商用化を公的に宣言している。そう、時代は「水素」なのであって、シェールであろうが何であろうが、化石燃料ではもはやないのである。
しかしそれを真正面から追求すると、アメリカはイギリスから何をされるかわからない。それをアメリカが最も恐れているであろうことは、中東の石油利権を争ってきたのが、ほかならぬ米英両大国であったことを思い起こせばすぐわかるのである。だからこそ「シェール革命だ」とアメリカは騒ぎ、「高貴な嘘」をついていると考えると合点が行く。
わが国にとって今、必要なのはバカの壁に入ることなく、老練な米欧各国が国際場裏で公然とつく「高貴な嘘」をあらかじめ見破り、私利私欲を捨てて人知れず備えるべく全国民を指導するリーダーなのである。今夏行われる参議院選挙の本当の争点は、実のところ「この一点」なのである。そのことを私たち有権者は忘れてはならない。




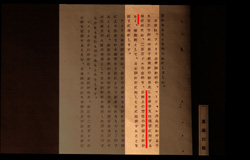


 Follow me on Twitter
Follow me on Twitter