2018年6月12日にシンガポールで行われた歴史的な米朝首脳会談の評価が日本では総じて低いようである。
例えば、6月13日の朝日新聞の社説は、「その歴史的な進展に世界が注目したのは当然だったが、2人が交わした合意は画期的と言うには程遠い薄弱な内容だった。最大の焦点である非核化問題について、具体的な範囲も、工程も、時期もない。一方の北朝鮮は、体制の保証という念願の一筆を米大統領から得た。公表されていない別の合意があるのかは不明だ。署名された共同声明をみる限りでは、米国が会談を急ぐ必要があったのか大いに疑問が残る。」と書いている。
北朝鮮のミサイル発射でJアラートまで駆使して半島有事を煽っていた、ちょっと前までの日本政府の現状を考えれば、この会談によって朝鮮半島有事が取りあえず遠のいたことをまず、評価すべきなのにこの社説はでは、全くそのことに触れていないのも不思議なところである。しかし、その後の韓国、北朝鮮、中国、ロシアの活発な外交交渉の展開、マティス国防長官による米韓軍事演習の無期限延期などの発表を見ると、明らかに大きく歴史は動き出している。
考えてみれば、日本のマスコミは先の米国大統領選においてもトランプ氏が大統領になることをほとんど予測していなかった。ヒラリー女史が当選し、今までと同様の米国の国際戦略が続くことを当然のこととしていたのである。そのためにトランプが何をしようとしているのか、何の為に大統領に選ばれたのかを、いまだに全く理解しようとしていない。
それでは、彼はどういう役割を担って大統領になったのか、それを考えるためには第二次世界大戦以降の世界経済の変遷を振り返る必要がある。大戦後、すべての技術、お金、金(ゴールド)、インフラがアメリカ合衆国に集中していた。そのため、西側諸国の経済は、米国が共産圏であるソ連に対抗するために豊富な資金、技術を、提供することによって離陸し、成長してきた。そして1965年以降、西ドイツ、日本が経済的に頭角をあらわすとともに、米国はベトナム戦争等の巨額の出費(これによって日本経済は高度成長した)もあり、いわゆるドルの垂れ流し状態に陥る。その結果、起きたのが、1971年のニクソンショックで、ニクソンは金とドルの交換の停止、10%の輸入課徴金の導入等の政策を発表し、第二次世界大戦後の通貨枠組み:ブレトン・ウッズ体制を解体、世界の通貨体制を変動相場制に移行させた。しかし、その後も米国の赤字基調は変わらず、1985年にはプラザ合意による大幅なドルの切り下げという事態に日本は共和党のレーガン政権時代に追い込まれる。貿易黒字を貯めこむ日本は、内需拡大を迫られ、その後、バブル経済が発生することになる。1965年以降、日米貿易摩擦が発生し、製造業間の調整交渉が日米両政府によって重ねられてきたが、80年代後半以降、米国はトヨタの負け(製造業)をソロモン(金融業)で取り返す戦略に転換。日本が貯めこんだドルを米国債、株式に投資させ、米国に還元させることで儲ける仕組みをつくりだした。この方式を新興国に当てはめ、始まったのが、現在のグローバル金融である。そして、グローバル金融を支えてきたのが、IT革命だ。つまり、賃金の安い新興国に米国企業が工場を作る投資をし、その製品を米国に輸出させた儲けは、米国の金融機関が吸い上げるという仕組みである。ポイントは、この仕組みを円滑に機能させるためには、米国のルール:新自由主義と新保守主義の思潮から作り出された価値観(ワシントンコンセンサス)をそれら、すべての国に受け入れさせる必要があり、軍需産業維持のための戦争と価値観の押し付け外交が密接に結びついていった点にある。つまり、そのルールを押し付けるためには、米軍が世界展開していることが好都合だったということである。ところが、2008年のリーマンショックでこのグローバル金融がうまく、機能しないことが露呈し、中央銀行制度ができて以来、初めての異常な金融緩和が始まったが、現在、それもすでに限界に達している。
この状況を打開するために選ばれたのがトランプなのである。
基本的なトランプの考え方は次の三つである。
(1)グローバル金融はうまく機能しない。
(2)アメリカは世界の警察官をやめ、世界に軍事展開することをやめるべきだ。
(3)金融で儲けることができないなら、米国内で製造業を復活させるしかない。
ということは、基本的にトランプは早く、米軍を世界から撤退させたい、そのためには極東の冷戦も早く終わらせるべきだと考えているということである。このような分析は日本のマスコミでは報道されることはないが、北朝鮮の金正恩はこのトランプの考えをしっかりと理解し、核カードという札を手にした時点で勝負に出てきた相当したたかな政治家であるという見方もできるのである。
もちろん、このような動きが進むことは、1945年8月15日以降の日本のあり方を根本的に変えることにも繋がっていく。このことを、マスコミを含む日本のイスタブリシュメントは、巨大利権化された日米安保体制(今は日米同盟体制という言葉に変わったが、)のなかで見たくない。それが日本のマスメディアの論調を左右する空気と今もなっている。考えてみれば、日本の戦後体制は、天皇実録を読み込んだ豊下楢彦氏が「昭和天皇の戦後日本:〈憲法・安保体制〉にいたる道」で明らかにしたように昭和天皇とマッカーサーの11回の会談で実際には決まってしまったようなものなのである。この冷戦下のなかで半ば独立を放棄し、経済的利益を追求する戦略はベルリンの壁が崩壊し、冷戦が終わるまでは、きわめて有効に機能した。本来ならば、この時点で世界情勢の変化に合わせて外交戦略も変えるべきものだったはずだが、長年にわたる日米安保を中心とした利権構造があまりにも強固なものになり、変えることができなかったのである。その意味では、安保利権者にとっては、極東における分断された朝鮮半島の存在はあまりに好都合だったと考えることもできるだろう。しかしながら、それもこの6月12日の米朝首脳会談で大きく変わろうとしている。考えてみれば、日本という国がこれほど太平洋側ばかりに顔を向けていた歴史は、日本の長い歴史のなかでほとんどない。多くの日本人は忘れてしまっているが、廃藩置県後の都道府県の人口は、明治時代までは新潟県が一番だったのである。日本海側は、決して裏日本ではなかったのである。その意味で本来のユーラシア大陸に顔を向ける時代の転換点が訪れているとも言えよう。
ところで、第二次世界大戦後、米国のアジア情勢分析のトップだったオーウェン・ラティモアは「アジアの情勢」(119P)のなかで、次のように書いている。
「アメリカの対日政策は、日本の歩む方向にアジアを進ませることができる、という仮説の上に立っている。仮説の連鎖の第一環は、日本をアジアの工場とロシアに対する防壁とに仕立て上げることができる、と言う考えである。この仮説は、アメリカの政策の道具として日本は、イギリスとドイツとネパール王国とが持つすべての価値を、一身に兼ね備えているという驚くべき理論の上に立っているのだ。日本はイギリスと同じように据え付けの航空母艦として使うこともできるし、ドイツと同じように周囲のどれよりも発達した工業を持っているので、ドイツのように付近の主な国々の工業の発達を利用し、またそれを反ロシア的方向に誘導するための中心とすることができる。インドから独立しており、インドとイギリスに凶暴なグルカ人傭兵を供給しているネパール王国と同じように、生まれつき訓練された日本人は、<伝統的に反ロシア的>であるから、時と共に、独自の政治を持たず、自国の<作業場>をまかなってくれるアメリカに対して堅い忠誠を致すところの、新しい植民地軍隊を供給する国になるだろう、と期待されているのである。」
如何だろうか。オーウェン・ラティモアはこんなことは、アメリカの都合のいい幻想に過ぎないと分析しているにもかかわらず、現在の日本が1949年1月に書かれた文章の通りの日本になっていることに戦慄しないだろうか。
何れにしろ、極東における冷戦が終わろうとしている現実、すなわち日本の戦後が終わることを冷静に受け止める歴史的な時を迎えようとしている。
*オーウェン・ラティモア
(Owen Lattimore、1900年7月29日 – 1989年5月31日)は、アメリカ合衆国の中国学者。第二次世界大戦前には太平洋問題調査会(IPR)の中心的スタッフを長くつとめ、また戦時期には中華民国の蒋介石の私的顧問となるなど合衆国の対中政策の形成に関与していたため、戦後はマッカーシズム(赤狩り)の標的の一人となり迫害を受けた。1942年、中央アジアの探険、研究に対して、イギリスの王立地理学会から金メダル(パトロンズ・メダル)を贈られた。
The Situation in Asia(1949年)


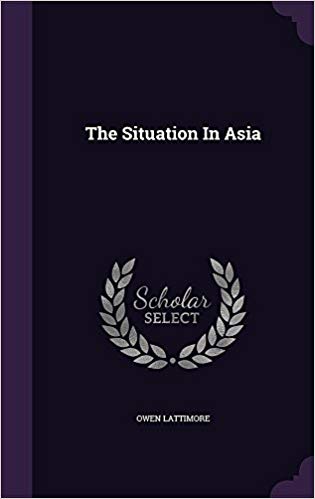
 Follow me on Twitter
Follow me on Twitter